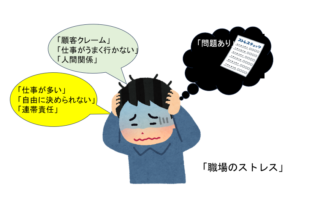「生産性が低い」という問題を解消する有効な課題設定のための4つの視点

「生産性が低い」という問題を解消する有効な課題設定のための4つの視点
「生産性が低い」という問題を解消する有効な課題設定のための4つの視点
「生産性が低いのは、システム化が遅れているから」
「ベテラン社員が退職して、生産性が落ちた」
職場には、様々な「問題」があります。その内の1つが、「生産性が低い」という問題があります。「生産性」には、様々な定義がありますが、ひとまずこの場では、
生産性=アウトプット量/一人当たりの拘束時間
と定義してみます。つまり、1日会社にいて、「どれだけモノを作ったか」、「書類を作成したか」、といったことを生産性とします。(アウトプットを金額で定義すると、商品の価格が生産性に影響しますので、この記事では量のみで考えます。)
「生産性が低い」という「問題」を考えるとき、冒頭に挙げたような「システム化が遅れている」などと安直に原因を考えてはいけません。システムを導入しても、そのシステムを使う時間が1日5分といった場合は、大きな生産性向上は期待できません。ベテランが退職しても、マニュアルがしっかりしていれば、さほど生産性の低下は起きません。
そもそも「問題を解決する」とは、問題の原因を突き止め、それを改善することです。つまり、生産性が低い問題を解決するとは、生産性の低い原因を突き止め改善するということです。
更に言えば、「問題」とは、「あるべき姿」と「現状」のギャップです。 その「問題」を解決していくために具体的に取り組むべきことが「課題」です。(参考記事:「ビジネスの問題解決は、「問題」と「課題」の違いと理解することから始まる」)
「問題をいかに適切な課題にすることができるか」ということが、問題解決のためには必要です。つまり、職場で「生産性が低い」という問題があるとすれば、その原因探し、その「原因」を解決する手段として「課題」が設定できます。
ところが、問題の「原因」を探っていくのは、容易ではありません。1つ2つの原因は、すぐ分かります。しかし、その奥に隠れた「気付きにくい原因」、「より深いところにある真の原因」を見つけることは容易ではなく、根本的に問題を解決ができないケースが多々あります。
「なぜ?なぜ?・・・を5回繰り返せ」
とは、トヨタのQC活動でよく使われる言葉です。工場のトラブル解決などにおいて、原因追及に、「なぜ?」を5回繰り返す手法は、とても有効です。 (参考記事:「トヨタ人の合言葉「なぜなぜ5回」の威力」)
事務職場や会社全体の生産性といった複雑で総合的な問題のおいては、一方向に「なぜ?」を繰り返しても原因があり過ぎて、何を取り上げ課題とするかの判断は難しいものです。
そこで、職場の問題に対して原因を見いだし、課題を設定するための4つの視点があります。
1)ムダな時間・費用
2)業務プロセス
3)社内規程や慣習
4)社員の習熟度
これら4つの視点から、問題の原因を検討することで、適切な課題を設定し解決策を見いだすことが期待されます。
この記事は、長年生産性改善に取り組んできた経験を元に書いています。
ムダな時間・費用
生産性を考える上で、ムダな時間、ムダな費用を見つける視点が重要です。
仕事をしている当事者は、ムダと思っていなくても、アウトプットにカウントできないことをする時間はムダです。
例えば、材料や資料を待っている間の手待ち時間、人やモノの移動時間、設備故障の復旧時間などがこれに当たります。
これを、「東京から車で福岡まで車で移動すること」を生産性に置き換えて考えてみると、車を運転していない休憩時間や給油時間、信号待ちや渋滞時間などが、ムダ時間にあたります。(必要な時間ですが、車を走らせることに寄与しない時間)
生産性を考える時、実際にアウトプットに寄与している時間の割合を調べると、事務職では50%、工場の社員でも70%を超えていないといったことは珍しくありません。データを取るのは、少々手間ですが、カメラ映像やパソコンの履歴等を利用して調べてみるとムダ時間を把握でき、生産性改善のヒントが得られるかも知れません。
業務プロセス
生産性において、仕事のやり方である「業務プロセス」に注目する必要があります。例えば、IT技術を活用してDXを進め生産性を上げようとしても、今のやり方(業務プロセス)を変えなければ、大きな改善効果が得られないことが知られています。(単にデジタル化しただけ)
業務プロセスは、車移動の例でいえば、「走行ルートをどう選択するか」ということになります。距離優先にするか、高速道路優先にするか、山道を避けるかと言った選択肢があるように、業務プロセスにも選択肢があります。
業務の重複、手戻り、業務手順、業務分担などのプロセスに注目して生産性の低い原因をみつけ、適切な課題を設定することです。
また、業務プロセスを考えるとき、他部署や他社との関係も含めて考えることが重要です。
社内規程や慣習
旧来の規程やルールが柔軟な働き方を阻害し、生産性を落としていることがあります。
コロナ禍後、ハンコの要求がぐっと減りました。また、リモートワークが一般化し、フレックスタイム制も増えています。
同じ会社、同じ職場で長く仕事をしていると、各種規程や習慣が当たり前となって、疑問を抱くことが少なくなっています。
「なぜ、こんな規程があるの?」
「なぜ、こんなことを続けているの?」
といった疑問を抱きながら、毎日の業務内容を見直すことで、問題の原因が見つかるかも知れません。
一度、事故や失敗をすると、その防止対策として、過剰な規程を設けていることがあります。時間がたち、生産の方法が変わったにも関わらずそのルールがそのままということがあります。
かつて、材料試験データの転記ミスがあり、顧客にご迷惑をかけたことが、私の職場にありました。そこで、データをお客様に届ける場合は、本人と上司(第三者)による「ダブルチェック」をすることを対策として顧客に約束しました。その後、データ収集が自動化され転記という手作業は消滅したのに、顧客との契約が変更されず長い間「ダブルチェック」を続けていたという事例があります。
社員の習熟度
同じ仕事をしても、その生産性には個人差があります。「出来る社員」「ベテラン社員」と言われる人の生産性は、総じて高いものです。
生産性の向上活動の中で、ある仕事を何時間で完了させることができるか、統計をとってみると驚くほど差が出ます。ところが、経験を積むことで、誰しも仕事が速くなります。
ルーチンワークは、その仕事を始めたばかり人は、時間がかかります。しかし、経験を積むにしたがって習熟度が上がり、仕事が速くなります。非定常作業においても、経験が多い人は、類推を働かせることで要領よくこなす可能性が高いものです。
パソコンソフトの利用や社内のシステムの利用などIT技術を活用するにしても、個人の習熟度の違いで生産性に大きな差が生じます。
業務マニュアルの整備、定期的な研修、OJTなどを活用して、個人レベルで仕事をスピードアップすることが、課題になります。
先ほど挙げた車による移動の例では、社員の習熟度とは、車の速度に当たります。運転時間を最大限確保し(ムダ時間の排除)、車の走行速度を上げることが到着時刻を早める、つまり生産性のアップになります。
まとめ
職場の問題に対して、原因を見いだし課題を設定するための4つの視点があります。
1)ムダな時間・費用
2)業務プロセス
3)社内規程や慣習
4)社員の習熟度
これら4つの視点から、問題の原因を検討することで、適切な課題を設定でき問題の解決策を見いだすことが期待されます。