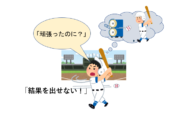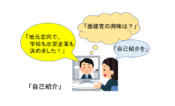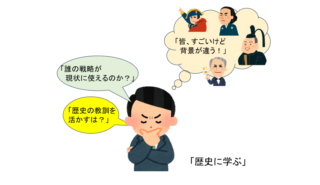「財源源がない」「人がいない」「時間がない」という「制約思考」の問題点

「財源源がない」「人がいない」「時間がない」という「制約思考」の問題点
無意識の「足りない前提」がもたらす3つの例
「医療制度を充実させたいが、財源がない」
「新規サービスを始めたいが、人手がない」
「旅行したいが、時間がない」
こんな外的条件を理由に、行動や意思決定を停滞させることは日常茶飯事です。政府の「やりたいけど予算がないからできません。」
は、最強の言い訳でしょう。
「やりたいことがあれば、財源をセットで用意してください」
と財務省は開き直り、防衛費や災害復興にあたってセットで「財源確保法」なる法律までつくってしまいました。「○○不足」を理由に行動を止めたり、その枠内でのみ思考したりすることで、発展が阻害されていることは様々な場面で見ることができます。
このような外的条件を理由に、行動や意思決定を停滞させる認知的枠組みを「制約思考」または「不足思考」と呼ぶことにします。
「制約思考」は、予算・人手・時間などの不足を前提に「できない」と判断し、行動や思考を止めてしまう心のクセというができます。この思考は、意識的されることもありますが、多くの場合は無意識のうち適用され、現実の制約以上に自らの可能性を狭めてしまうことになります。
この「制約思考」が無意識に作用している例は、歴史や社会のさまざまな場面に見出されます。
例えば、
1)戦国時代の領地争い、
2)社会主義的なパイの配分論争、
3)企業・個人の借金忌避論、
といったことです。この記事では、この3つの例を取り上げ、
「資源は限られており、それを奪うか守るしかない」
という発想が、どう行動様式に影響を与えたかを見た上で、その対処法を考えます。
戦国時代の領地争い:ゼロサム思考
戦国時代(15〜16世紀)における大名同士の戦いは、基本的に「領地の奪い合い」というゼロサムの発想の上に成り立っていました。ある大名の領地を増やすには、他者から奪うしかないという発想です。これは、制約思考の最も原初的かつ暴力的な表れでしょう。
ところが、「土地は有限である」という思い込みを脱却した人々もいました。多くの戦国大名の頭の中では、「領地=年貢収入=軍事力」という図式が成立していました。戦国大名たちが「土地の広さ=力の全て」と考えている限り、領地をめぐる戦いは続きます。ところが、戦国末期まで生き延びた武将達は、富が土地の広さだけに依存するものではないことに気付いていました。
例えば、石見銀山を持った毛利氏、甲斐金山を持つ武田氏、伊豆金山の北条氏などは、その力の根源を農業以外に持っていました。織田信長は楽市楽座による市場経済の活性化、堺や熱田を通した貿易など、農地の拡張以外の富の創出を行っています。面白いのは、信長が戦の恩賞に茶器など高価な品を使ったとの話があることです。これは、「土地以外にも、富がある」と示したようなものです。
天下を取った豊臣秀吉は、全国の金山銀山を手に入れたのですが、なお朝鮮出兵をしました。挑戦出兵は、秀吉の野心も有ったでしょうが、国内に新たに領地となる土地が無くなった中、武士達が、大陸にそれを求めたことが背景にあります。(井沢元彦著「逆説の日本史 11巻」による)
武士たちの
「奪わなければ、領地は増やせない」
という思考は、制約思考の産物です。
現代では、香港やマンハッタンの高層ビル群、オランダの干拓地や日本各地の埋め立て地、東京の地下鉄網などをみれば、技術が土地の有限性を打ち破ることが不可能ではないことがわかります。
広告

逆説の日本史11 戦国乱世編/朝鮮出兵と秀吉の謎 (小学館文庫)
社会主義的パイの配分論争:「足りない前提」が引き起こす対立
近代以降の社会思想では、社会主義と資本主義の対立は「富の分配」を巡る根源的な問題でした。社会主義者は
「一部の資本家が富を独占しており、労働者に正当に分配されていない」
と主張し、それに対し資本主義側は、
「競争によって富は拡大する」
と反論していました。この議論において、社会主義者には、
「経済のパイは有限である」
という前提が強く作用していました。つまり、「誰かが多く取れば、他の誰かが損をする」というゼロサム的な視点です。
この制約的な見方は、福祉や累進課税といった制度設計には一定の合理性を持たせましたが、一方で富の創出という視点を軽視することになりました。結果として、制度疲労や経済停滞に陥った国家(旧ソ連、東ドイツなど)も少なくありません。
逆に、資本主義国が「成長によってパイを拡大し、結果的に分配の余地も広がる」という発想を取り入れたことで、経済発展と生活向上の両立が一定程度可能となった事実があります。(たとえば戦後日本の高度経済成長期や鄧小平以降の中国など)
もちろん、資本主義にも格差や不平等という副作用があります。しかし、ここで重要なのは、「パイを拡大する」という視点があるかないかです。社会主義的配分論は、「制約されたパイ」の存在を前提に組み立てられた思想体系であり、その発想が無意識に浸透することで、成長の可能性を最初から否定してしまう危うさをはらんでいました。
企業・個人の借金忌避:財務的制約思考とリスクの過大評価
現代の日本において、企業や個人が「借金は悪いこと」と考え、必要な投資や挑戦を避けてしまう傾向が根強くあります。これは、戦後の金融危機やバブル崩壊、さらには教育における「借金=堕落」の価値観の刷り込みなどが影響していると考えることができます。
たとえば、中小企業において「手元資金がなければ設備投資できない」「補助金がなければ事業は始められない」という発想が多く見られます。しかし、ファイナンスとは本来、将来のキャッシュフローを信じて「今」資金を調達し、行動するための手段です。
また、個人においても、住宅購入や教育投資に対して「借金をしてまでやるべきではない」と考える人が少なくありません。これは、リスクを過大評価し、「失うこと」に過敏になる一方で、「得られること」に対して冷淡であるという心理的バイアス(損失回避バイアス)が関係していると考えられます。
日本においてMMT(現代貨幣理論)に対する反発が強いのも、この「制約思考」が深く根を下ろしているためかと思えます。つまり、「信用創造」が理解されていないということです。多くの人々が「国家財政も家計と同じ」と誤解し、「借金は将来世代のツケ」と考えがちです。実際に財務省やマスコミが、洗脳しています。このために、国家としての柔軟な財政運営や成長投資ができなくなっています。
実際には、将来の生産力や成長性が見込まれる場合、負債は必ずしも悪とは言えません。国が負債として、貨幣を供給すること(信用創造)により、経済が発展していきます。重要なのは、「資金をどう使い、どう回収するか」という設計力であり、「そもそも借金をしない」ことではありません。
まとめ:制約思考は、気付かないうちに入り込む
戦国時代の領地争い、社会主義的な分配論、現代の借金忌避に共通するのは、「資源は限られており、奪い合うしかない」という前提に基づいた行動です。この前提は多くの場合、明確に言語化されることはなく、無意識のうちに行動様式や制度設計に影響を与えます。
このような思考が根づくと、人々は「どうすれば増やせるか」「どうすれば乗り越えられるか」を考えなくなり、資源(財源)の「取り合い」と「守り合い」が続き、本来可能であった創造や成長の道が閉ざされていきます。
制約思考を乗り越えるには、まず「その前提は本当に正しいのか?」と疑う力が必要です。そして、制約を前提にしながらも、それを「設計し直す」視点と、「超えていく」意志が求められます。
参考記事:仕事や生活において「制約」を喜んで受け入れると創造的発想が広がる
誤解の多いMMT理論(現代通貨理論)の本質は、「貨幣とは借用書」と理解すること