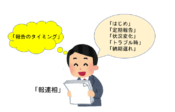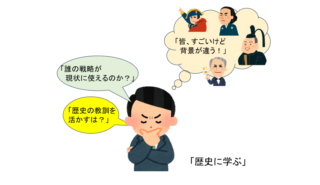「話し合い」がうまくいかない4つのパターンとその理由

「話し合い」がうまくいかない4つのパターンとその理由
「話し合い」がうまくいかない4つのパターン
「反対者がいて進まない道路工事」
「決まらない会議」
法律的には、政府や自治体は強制力を発揮して工事を進めることができるのですが、実際には反対者を無視できず時間を要します。会議も上位職位者が決めるか、多数決で決めればいいのですが、「全員が納得するまで」まで会議が続くことがあります。
そこには、日本的といえる「話し合い絶対主義」の原理が、働いています。
日本人の「話し合い絶対主義」とは、井沢元彦氏や山本七平氏が言うところでは、
① 物事は、話し合いで決めることが正しい
② 話し合いで決めたことは、正しい
③ 全員一致が正しい決め方
などの特徴をもった考え方です。
ところが、いくら「話し合い」をしても、解決しない場合があります。また、話し合いで決めたことが、必ずしも正解ではありませんし、いくら時間をかけても全員が一致することが出来ないこともあります。特に領土問題や宗教のからむ国際問題は、長年いくら外交交渉をしても何の進展も見られないことばかりです。
「話し合い」は、前提が対立していたり、価値観が根本的に異なっていたりした場面、ほとんど機能しません。話し合いが、うまく行かないパターンが4つあります。
1)力の差が大きい関係
2)ゼロサムの利害対立があるとき
3)価値観が根本的に異なる関係
4)相手が「対話をする気がない」
これらの状況下での「話し合い」は、合意を得ることが極めて難しいものです。それでも「粘り強く話し合い」を続けても、話し合うことが目的化するだけで、得るものはないと覚悟すべきでしょう。
この記事では、「話し合い」がうまく行かない4つのパターンとその理由をご紹介します。
力の差が大きい関係では、対等な話し合いはできない
大国と小国、上司と部下など両者に大きな力の差があるとき、対等な話し合いは不可能です。
たとえば、南シナ海において中国は、南沙諸島などを実行支配しています。フィリピンは、領有権を主張していますが、力の差があり過ぎて、話し合いにはなっていません。
パワハラや下請けいじめは、上司と部下、大企業と下請け企業といった力の差があって生まれます。同等な立場で話し合うことは、まずできません。同等に話をしようとすると、第三者の介入や下請け法といったサポートがなければ、難しいと言えます。家庭内暴力(DV)も同様で、当事者間の話し合いだけでは解決できるものではありません。
戦争や紛争における停戦交渉は、どちらかが負けを認めざるを得ない状況か、力が拮抗して膠着状態に入らなければ、うまく行かないことは歴史が証明しています。平和運動家が、戦況を考慮せずに「即時停戦」を訴えても効果はありません。
ゼロサムの利害対立があるとき
国家間の領土問題、分割できないものをめぐる問題などの話し合いにおいて成果を出すには、構造的に片方が譲るしかありません。
互いに「譲れない一線」があり、これが重なるようであれば、いくら話し合いをしても妥協点を見つけることは、極めて困難です。
ウクライナとロシアの戦争では、「譲れない一線」が両国で重なり、停戦が見えていません。(2025年4月時点)戦争がゼロサムではなく、例えば失った領土は、別の場所で確保できるといった条件があれば、いいのですが、そうはなりません。
ゼロサムの利害対立があるときは、交渉者の権限の大きさが重要です。国家間、企業間、組織間のゼロサムの利害対立がある問題での話し合いは、代表者に決める権限をもっていなければ、交渉がまとまりません。戦国大名や帝国時代の独裁者なら、自らの権限で譲歩して交渉をまとめることができます。ところが、民主主義と言われる体制では、譲歩することに対して、国民やマスコミの反発があります。これを押さえる力がなければ、交渉はまとまりませんが。日露戦争の講和条約に反対をきっかけとした日比谷焼き討ち事件は、外交交渉の際の世論やマスコミの影響力を示しています。代表に対する権限委譲と小村寿太郎ほどの覚悟がなければゼロサムの交渉ができません。第2次大戦の終戦は天皇御聖断によってなされましたが、これもまた昭和天皇に御覚悟があったから成し得たものです。
価値観が根本的に異なる関係
善悪や価値観が根本的に異なる関係において、合意形成をすることは極めて難しいことです。例えば、宗教対立は典型的な例です。
明確な宗教ではなくても、
「原子力発電を絶対認めない」
「軍事力を持つべきではない」
と考える人の中には、これらを理屈抜きで正しいと信じている人々がいます。この場合、それは宗教と同じです。いくら、話し合いをしても、これと意見の異なる人と合意点を見つけることはできません。ややこしいのは、価値観が根本的に異なる関係では、話し合いで合意点を見つけるのが困難であるにも関わらず、「話し合い絶対主義」であることです。
「どんな人とでも、話し合えば分かってもらえる」
と互いに勝手に思い込んでいると、益々不毛な話し合いが続いていきます。
「話し合い」で問題が解決するのは、価値観を共有していて、互いに合意点があると信じているからです。商売が成立するのは、貨幣価値が共有されていて、価格で折り合いがつく点があると双方が思っているからです。「カネで買えないもの」を売り買いすることは、不可能です。例えば、「愛情」や「憎しみ」の売り買いはできません。
ウクライナとロシアの戦争において、ロシア軍の戦死者は、ウクライナ軍の4万人に対してロシア軍は、20~25万人といわれています。(ニューズウィーク:「ロシア軍の死傷者数が歴史的規模で増加…第2次大戦に次ぐ、その数とは?」)死者の数ではウクライナの勝ち、占領地の広さではロシアの勝ち、と言った具合には、停戦交渉はできません。どちらも、自分達なりの価値観のもとで戦争をしているので、どちらかが敗戦を認めるか、戦闘が膠着状態にならない限り、停戦は難しいと言わざるを得ません。
相手が「対話をする気がない」
対話をする気がない相手とは、話し合いは成立しません。対話をする気がないのは、価値観が違う、圧倒的に力の差があるといった背景のもと、
「話し合いをしても得るものがない」
という判断です。
相手が「対話をする気がない」のに、形だけの会議をして、
「今後も会話を続けることに合意した」
などとコメントする国際会議はよくあることです。
特に日本では、「話し合い絶対主義」が浸透しているので、そうでもコメントしないと皆が納得しないという状況があります。
また、交渉したくても
「テロリストとは交渉しない」
「誘拐犯に譲歩しない」
といった国や警察の大原則があります。実際には、日本政府が水面下でテロリストや誘拐犯と交渉して譲歩し、後になって国際的に批判されることがあります。しかし、日本では「話し合い」をしなかった方が、批判が大きくなるかも知れません。これも、「話し合い絶対主義」が浸透しているためでしょう。
まとめ
「話し合い」は、前提が対立していたり、価値観が根本的に異なっていたりした場面、ほとんど機能しません。話し合いが、うまく行かない4つのパターンがあります。
1)力の差が大きい関係
2)ゼロサムの利害対立があるとき
3)価値観が根本的に異なる関係
4)相手が「対話をする気がない」
これらの状況下での「話し合い」においては、合意を得ることが極めて難しくなります。「話し合い」は道具であり、それを絶対視して「すべてを解決できる」と思い込むのは危険。状況に応じて、制度による強制力、第三者の調整、対立を乗り越える決断や介入、ときには中断が必要です。