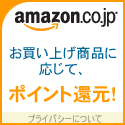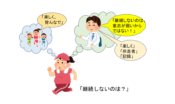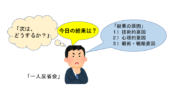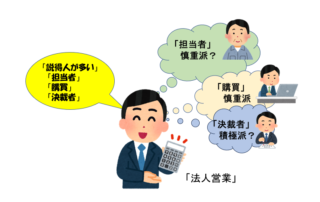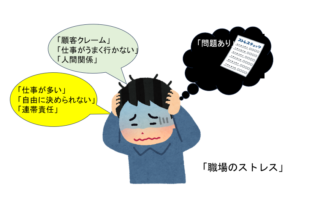「同調圧力」は、どこの国にも存在。日米の同調圧力の違いを考える

「同調圧力」は、どこの国にも存在。日米の同調圧力の違いを考える
「同調圧力」は、どこの国にも存在。日米の同調圧力の違いを考える
「会議で大勢に反する意見を言うことが難しい」
「イベントに誘われて断りにくい」
これらは、職場で直面する「同調圧力」です。最近は、堂々と多数派意見に異を唱える人、イベント参加を断る人が増えてきたような気がします。しかし、一方でコロナ禍の時期の自主警察やSNS上には、強烈な同調圧力と言うべき意見が溢れています。
「同調圧力」とは集団の中で起こる心理的な圧力で、少数意見を持つ人に対し、多数意見に合わせるよう暗黙のうちにプレッシャーを与えることをいいます。会議中に多数派とは違う意見を言えない雰囲気があったり、多くの人が参加するイベントへの参加を断れなかったりするケースです。
同調圧力は、日本独特のように感じる人も多いかも知れませんが、国や文化を問わず存在します。人間が集団で働き生活する以上、一定の協調や共通理解が求められるのは自然なことです。
私自身が、米国に住み、生活をしていた経験からすると、日米ともに「同調圧力」はあるものの、その圧力のかかり方や、個人がそれにどう向き合うかは、文化的背景によって大きく異なっていることを実感しました。
例えば、日本では、会議や打ち合わせの場で「意見を合わせる」ことが重視される傾向があります。対立を避け、和を保つことが美徳とされる文化の中では、異なる意見を述べること自体が「空気を読めない」「協調性がない」と受け取られることもあります。結果として、個人の本音や創造的なアイデアが抑制される場面が少なくありません。
一方、米国では、会議の場で「自分の意見を言う」ことが強く求められます。沈黙は「関心がない」「貢献していない」と見なされることがあり、多少でも違う視点を提示することが「積極性」「主体性」の証とされます。つまり、日米ともに同調圧力は存在しますが、その意味合いが大きく異なります。
日米で同調圧力を比較すると以下のような差があります。
1)日本の同調圧力は、「意見を合わせろ」
2)米国の同調圧力は、「何か言え」
3)日米の差は、同調圧力の受け止め方
日米とも「同調圧力」は、ありまが、その受け止め方の差、同調圧力に逆らった人に対する周囲の考え方が違います。米国における同調圧力の差を知ることで、同調圧力への対応のヒントが得られることを期待します。
この記事は、日米で生活、仕事をした経験を基に書いています。
広告
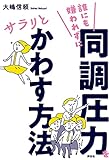
誰にも嫌われずに同調圧力をサラリとかわす方法
日本の同調圧力:「意見を合わせろ」
日本の職場では、「みんながそう言っているから」「前例があるから」「上司の意向だから」といった理由で、意見を合わせることが求められる場面が多くあります。これは、集団の調和を重んじる文化に根ざしたものであり、個人の意見よりも全体のまとまりが優先される傾向があります。
このような環境では、異なる意見を述べることに心理的なハードルが生じます。たとえ建設的な提案であっても、「反対している」「否定している」と受け取られる可能性があるため、結果として沈黙を選ぶ人が増えてしまいます。
違う意見を言ったり、皆が参加するイベントに行かなかったりということが出来ないのは、その裏に「和を乱す人」と思われたくない、「共感出来る人、いい人でありたい」といった気持ちが強く働いています。
このような同調圧力は、短期的には摩擦を避ける効果がありますが、長期的には創造性や問題解決力を損なうリスクがあります。多様な視点が出づらくなり、組織の硬直化を招く可能性があります。
米国の同調圧力:「意見を言え」
一方、米国の職場では、「自分の意見を言う」ことが強く奨励されます。会議の場では、沈黙していると「何も考えていない」「関心がない」と見なされることがあり、多少でも違う視点を提示することが「積極的な参加」として評価されます。
この文化では、「同調すること」よりも「貢献すること」が重視される文化に基づきます。たとえ意見が少数派であっても、それが論理的であれば尊重される傾向があります。むしろ、全員が同じ意見を述べることに対して「本当に考えているのか」「忖度しているのではないか」と疑問を持たれることさえあります。
実際に米国人達と仕事をして分かるのは、意見を言わないことで、「無能な奴」と思われることを嫌う気持ちが強くあることです。意見を言わない日本人に対して、影で「奴は理解しているのか」「能力を疑う」といった言葉を聞いたことがあります。努めていた会社が、上場している会社で高学歴の社員が多かったこともあるかも知れませんが、とにかく「無能」と思われることを極度に嫌う気質がありました。
米国人の感じる「何か意見を言わなくては」という同調圧力は、結構強いものがあります。結果として、どんな会議でも同調圧力が「沈黙を避ける」という方向に働き、見かけ上は活発なものとなります。残念ながら、中身の薄い発言も多くありますが。
同調圧力にあがなうことへの評価の違い
日米、それぞれ同調圧力がありますが、注目すべきなのは、その圧力にあがなったときの「評価のされ方」の違いです。
日本では、同調圧力に逆らって意見を述べると、「空気を読めない」「協調性がない」といったネガティブな評価を受けることがあります。特に、会議の場で上司や多数派の意見に異を唱えると、場の雰囲気を乱す存在として扱われることもあります。
一方、米国では、同調圧力に逆らって意見を述べることが「主体性」「独立性」として評価されることが多くあります。もちろん、言い方やタイミングによっては反発を招くこともありますが、基本的には「意見を持っていること」自体がポジティブに受け止められます。
この違いは、職場での心理的安全性にも影響します。米国では、「自分の意見を言っても嫌われない」「評価が下がらない」という安心感があるため、自由に発言しやすい環境が整っています。日本では、「言ったらどう思われるか」「場を乱さないか」といった不安が先立ち、結果として沈黙を選ぶ人が増えてしまいがちです。
日米の同調圧力の構造的違い
同調圧力の違いは、文化的背景だけでなく、組織構造や教育のあり方にも起因しています。
日本では、学校教育において「協調性」「集団行動」が重視される傾向があります。意見を述べるよりも、場を乱さずに行動することが評価されるため、社会人になってもその価値観が根強く残ります。
米国では、教育の段階から「自分の意見を持つこと」「異なる視点を尊重すること」が奨励されます。ディベートやプレゼンテーションの機会が多く、意見を述べることが「当たり前」の行動として定着しています。
また、組織の意思決定プロセスにも違いがあります。日本では、根回しや合意形成が重視されるため、会議の場ではすでに方向性が決まっていることが多く、異論を述べる余地が少ない場合があります。米国では、会議の場で議論を通じて意思決定を行うことが多く、意見の違いが前提とされています。
まとめ
同調圧力は、どの国の文化にも存在します。しかし、その圧力の方向性と、それに逆らったときの評価は、文化によって大きく異なります。
日本では、「意見を合わせる」ことが求められ、異なる意見を述べることに慎重になる傾向があります。米国では、「意見を言う」ことが求められ、沈黙することにプレッシャーを感じることがあります。
重要なのは、どちらの文化でも「自分の意見を持つこと」「それを適切に伝えること」が、個人の成長と組織の活性化につながるという点です。同調圧力に流されるのではなく、自分の軸を持ち、場に応じた伝え方を工夫することで、より健やかで創造的な職場環境を築くことができるのではないでしょうか。
参考記事:日本にあるある、過剰な「同調圧力」による「スパイト行動」などの弊害
「町内会あるある」とメンバーが辞めたくなるほど不快になる原因