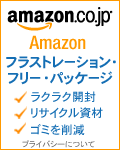「戦略系コンサルタント」を使う4つメリットとデメリット

「戦略系コンサルタント」を使う4つメリットとデメリット
「経営戦略系コンサルタント」と「専門系コンサルタント」
「経営コンサルタント」
「ITコンサルタント」
「人事コンサルタント」等々
こんなコンサルタントやコンサルティング会社が、巷に溢れています。また、コンサルティング会社は、新卒の就職戦線でも高い人気を誇っています。
そんなコンサルタント(以下、コンサル)は、対象とする相手、内容も掲げている「名前」も様々ですが、大きく「経営戦略系」と「専門系」に分けることができます。この2つは、それぞれの役割とアプローチに明確な違いがあります。
経営戦略系コンサルは、企業の中長期的な成長や競争優位の確立を目的として、経営者層と密接に連携しながら戦略立案や意思決定支援を行います。市場環境分析、業界構造の理解、競争戦略の設計、新規事業開発、組織改革など、全社的な視点から課題を抽出し、抽象度の高いフレームワークやモデルを駆使して意思決定を支援するのが特徴です。
一方、専門系コンサルは、IT、人事、会計、法務、物流など特定の機能領域に深い知見を持ち、現場レベルでの業務改善やシステム導入支援、制度設計など実務的な支援を行います。クライアントの担当部署と密接に関わり、具体的な課題解決や導入・運用フェーズでの定着支援に重きを置きます。
戦略系は、「どこへ向かうか」を描き、専門系は「どうやって進めるか」に力を発揮します。専門系は、コンサルを使う側もコンサルする側も共通の目的、目標が立てやすく、活用し易いものです。言ってみれば、スポーツのコーチのようなもので、長所を伸ばし、欠点を補うということです。
一方、戦略系は、課題として「会社をどの方向にもっていくか」ということであり、企業経営の根幹にかかわる問題を扱います。特に、スタートアップ企業や衰退企業など、経営の転換点を迎えている会社では、コンサルの活用次第で大きなメリットを生むことが期待できます。
戦略系コンサルを使うメリットは、以下の4つがあります。
1)企業が抱える「真の問題」が明確になる
2)内部からでは気付かない「ズレ」が修正できる
3)社内外の事象を論理的に分析できる
4)外圧として利用でき、大胆な改革を実行しやすい
一方デメリットとして
1)費用が高い
2)効果がすぐに見えない
3)外部依存とノウハウの欠如
といったことがあります。
この記事では、戦略系コンサルのメリット、デメリットについて、スタートアップと衰退企業の例を使いながら、コンサルの活用について考えます。この記事は、堀紘一/津田久資著「本物のコンサルを選ぶ技術」クロスメディア・パブリッシングを参考にしています。
広告

本物のコンサルを選ぶ技術
企業が抱える「真の問題」が明確になる
経営陣や現場が抱える問題は、しばしば「見えている問題」と「真の問題」とが異なっていることがあります。「見えている問題」が、実は「真の問題」の「結果」ということもあります。戦略系コンサルタントは、ヒアリング、データ分析、競合比較などを通じて、企業が本当に解決すべき問題を浮き彫りにすることが求められます。
例えば、創業期のスタートアップは、商品開発や資金調達に追われる中で、
「何が成長を阻んでいるのか」
を明確に捉えていないことが多いものです。コンサルタントが市場ポジショニングやターゲット顧客のズレを可視化することで、方向性を修正しやすくなります。
また、衰退企業では、長年の慣習や業界構造の変化に気づかず、
「なぜ売上が減っているのか」
という問題に対して、より深い原因(例:顧客の価値観変化、競争優位の喪失)を明らかにするといったことが可能です。
内部からでは気付かない「ズレ」が修正できる
社内の人間は、組織文化やヒエラルキーに影響されて「常識」や「当然」と感じてしまいがちな思考に縛られているものです。コンサルタントは外部の視点から、そうした組織内のバイアス、業界のバイアスに影響された「常識」と、「世間の常識」や、「他業種の常識」との「ズレ」を見つけ、修正を提案できます。
スタートアップにおいては、創業者の思い込みにより自社のモノやサービスとマーケットニーズとが乖離していて、失敗するケースがしばしば見られます。マーケットニーズではなく、自社のビジネスモデルに拘り続けるといった「ズレ」をコンサルは指摘します。
また、衰退企業では、「かつての成功体験」に依存した判断が多く、現代の競争環境と「ズレ」を生んでいることがあります。そうした「過去との断絶」を第三者が示唆できることは大きな価値です。
社内外の事象を論理的に分析できる
感覚や経験に頼りがちな判断を、データやフレームワークに基づき論理的に再構成することができます。コンサルタントは、仮説構築→検証→実行という手順で進め、社内の納得感と合理性を高める役割も担います。ただし、依頼して企業はそれぞれ異なる過去、現在を持っています。コンサルタントが、それに合った理論の応用ができるかといった「考える力」が問われます。
スタートアップは「スピード感」が重視される反面、意思決定が属人的になりやすく、論理の整合性が後回しになっていることがあります。戦略コンサルが入ることで、根拠のある意思決定が可能になります。
また、衰退企業では、「長年やってきたから」という前例主義が根強く、論理的説明が伴わない意思決定が多い傾向があります。戦略コンサルがMECEなロジックで再構成することで、経営陣の合意形成も進みやすくなります。
外圧として利用でき、大胆な改革を実行しやすい
組織内の改革は、社内の力学や抵抗によって進みにくいものです。しかし
「外部の専門家がこう言っている」
という形で外圧を導入することで、利害関係者の納得感を高め、大胆な変革を実行しやすくなります。
スタートアップでは、チーム内の合意形成が困難なとき、第三者の意見が舵取りの決定打になります。特に投資家対応や次の成長戦略などで、戦略系コンサルの提言は説得力を持ちます。
また、衰退企業では、既得権を持つ部門や役職者の抵抗が激しい場合、外部専門家の存在が「変革の口実」になります。現場との軋轢を回避しつつ、構造改革を進める助けになります。
戦略系コンサルを使うデメリット
戦略系コンサルを使う際、いくつかのデメリットがあります。以下、デメリットとその回避策を紹介します。
費用が高い
戦略系コンサルタントは、日単価で数十万円、プロジェクト単位で数百万円〜数千万円という費用がかかることがあります。特にスタートアップや中小企業にとっては負担が重く、費用対効果が見えにくいと感じられます。
スタートアップにおいては、外部に多額の費用を払うことに抵抗が生じがちで
「自分たちでやるべきでは?」
という思いが強くなります。スタートアップの提供するモノやサービスの開発と営業や組織運営といった経営とは、別物であるとの認識が必要です。高機能な商品を武器に起業した会社が、短期間で倒産してしまう例を見るまでもなく、経営戦略系コンサルの価値を認知機しておくべきです。
また、衰退企業では、既に収益性が低下していることが多く、
「まずは売上・利益を立て直してから」
と費用を抑える傾向があります。
戦略系コンサル費用は、起業や再建のための「投資」と考え、「利用する、しない」を判断することが重要です。
効果がすぐに見えない
コンサルタントの提言や戦略は、即効性があるとは限らず、中長期的な視点で実行されることが多いものです。従い、社内から
「何をしてくれているのか分からない」
と不満が出ることもあります。経営層が、利用の価値を総合的に判断することが重要です。コンサルは、
「数年先のために、今すぐ打つ手を教えてくれる」
と認識することです。
外部依存とノウハウの欠如
コンサルタントに業務や改革を「丸投げ」してしまうと、自社内部に戦略策定能力が蓄積されず、依存体質になる危険性があります。また、提言内容が実行段階で現場と乖離し、実効性が伴わないケースもあります。
コンサルと一緒なって、戦略を作成、実施していくことが重要です。
まとめ
コンサルは、大きく「戦略系」と「専門系」に分けることができます。この2つには、それぞれの役割とアプローチに明確な違いがあります。
戦略系コンサルを使うと以下の4つのメリットがあります。
1)企業が抱える「真の問題」が明確になる
2)内部からでは気付かない「ズレ」が修正できる
3)社内外の事象を論理的に分析できる
4)外圧として利用でき、大胆な改革を実行しやすい
これらのメリットを発揮できるコンサルを選択すること、利用する側もこのメリットを最大にする努力が必要です。