「問題だらけの会社」で、課題解決のための5段階のプロセスにおけるポイント
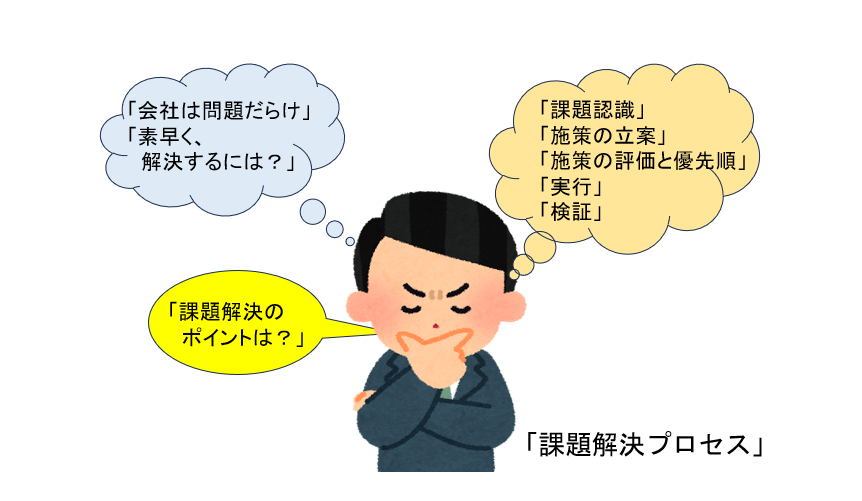
「問題だらけの会社」で、課題解決のための5段階のプロセスにおけるポイント
課題解決における5段階のプロセス
「収益の低迷、人手不足、顧客クレーム、社内の人間関係」
会社には、問題が溢れています。極論を言えば、「どんな社員も会社では、問題(課題)を解決することが仕事」と言うことができます。
「課題」とは、理想とする会社像や社員像と現実とのギャップです。理想(なりたい姿や目標)が高ければ、高いほどギャップは大きくなり、課題も大きいということになります。多くの課題に対して、効率よく解決していく能力には、人や組織により大きな差があります。いわゆる「仕事が出来る社員」「優れた組織」とは、課題解決の能力が高いことを指しています。ただし、課題解決能力といっても、解決した「課題」がどんなものかによります。順調に利益を上げていても、「今後成長するのか」、「予想される環境の変化に対応できるのか」といったことを「課題」として認識していなければ、いくら個別テーマの課題解決能力があっても意味をなしません。
本当の意味での課題解決能力とは、課題の認識から、対応する施策の立案・実施・検証・修正といったことが、出来るということです。つまり、いわゆるPDCAとその前の課題認識(課題の発見)がセットで揃って、課題解決能力といえます。
課題解決のプロセスは、以下のような5段階があります。
1)課題認識
2)施策の立案
3)施策の評価と優先順付け
4)施策実行
5)実行結果検証と修正
これは、一般的なPDCA(計画・実行・検証・修正実行)ということに、課題認識を加えています。特に重要なのは1)課題認識、2)施策の立案、3)施策の評価と優先順位付けの3つの段階です。これらは、いわば「戦略フェーズ」にあたり、全体の方向性と質を決定づける部分です。
しかし、現場ではこれらの段階が軽視されがちです。その理由としては、以下のような構造的要因が挙げられます。
①「早く動くこと」が評価される文化:
考えるよりも「とにかくやってみる」ことが重視され、思考の時間が確保されにくい。
②「成果主義」の誤解:
目に見える成果(売上、件数など)ばかりが評価され、思考や設計の質が評価されにくい。
③「属人的な判断」への依存:
経験や勘に頼った意思決定が多く、論理的な構造化や合意形成のプロセスが省略される。
課題解決というと、とかく施策の実行結果の検証に注目が集まります。世の中には、様々な課題に対する施策案、実行に関するノウハウが溢れていますが、課題認識の段階が軽視されているようです。
この記事では、課題解決の各段階のポイントと注意点をご紹介します。
広告
課題認識(問題を正しく捉える力)
課題認識において、「課題」は大きく分けて2つのパターンがあります。
1)外部提示型:
上司やクライアントなど、他者から課題が提示される場合です。
提示された課題の内容を受け取り側が正しく理解しているかが、重要です。上司の曖昧な指示のままに仕事をして、結果を提出すると、上司の期待するものと全く違ったものであったなどといった経験があります。
また、指示された課題が、問題の本質を捉えていない場合もあります。「言われたことをそのままやる」姿勢ではなく、「なぜその課題が重要なのか」「背景にある真の問題は何か」を掘り下げる姿勢が求められます。
2)自発発見型:
自ら現場やデータ、顧客の声などから課題を見出す場合です。
観察力や仮説構築力、現場との対話力が問われます。特に、表面的な現象に惑わされず、構造的な問題を見抜く力が重要です。経営戦略を立案するコンサルタントや経営者に求められる能力です。
課題発見には、ロジックツリーによる構造化が有効
課題を正確に認識するためには、ロジックツリー(論理的分解図)が非常に有効です。ロジックツリーには以下のような分解の視点があります。
1)足し算型(加算型)分解:
例)売上=商品Aの売上+商品Bの売上+商品Cの売上
→ どこに問題があるか(どの項目が落ちているか)を特定しやすくなります。
2)掛け算型(乗算型)分解:
例)売上=客数 × 客単価
→ どの要素を改善すれば効果が出るか、施策の方向性が見えます。
3)プロセス型分解:
例)受注→製造→出荷→納品
→ どこにボトルネックがあるか、業務フローの中での課題を発見できます。
課題認識段階での注意点と軽視されがちな点
課題認識は、課題解決プロセスの中でも最も重要でありながら、最も軽視されがちです。多くの現場では「すぐに解決策を出すこと」が求められがちで、課題の本質を深掘りする時間が取られません。しかし、誤った課題認識のもとで立案された施策は、的外れな結果を生み、リソースの浪費につながります。
施策の立案(創造的かつ現実的な解決策の設計)
課題を構造的に捉えた上で、課題の構造に応じた施策の発想が有効です。
1)加算型分解からの施策発想
例えば、事業内容を商品別に分解したとき、「弱い商品」「伸ばせる商品」といった発想で施策を立案できます。また、事業内容に対して、「自社が扱っていない商品」や「除くべき商品」といった発想もできます。
施策を立案する際には、以下のような視点が有効です。
2)掛け算型分解からの施策発想
例えば、「売上=客数×客単価」であれば、「客数を増やす」「客単価を上げる」「リピート率を高める」など、施策の方向性が明確になります。
3)プロセス型分解からの施策発想:
生産性の向上を考えるときプロセス型分解が有効です。業務内容をプロセス型分解し、ボトルネックが「出荷工程」であれば、「出荷人員の増強」「出荷システムの自動化」など、具体的な改善策が導き出せます。工場の生産現場に携わった経験では、プロセス型分解からボトルネック(課題)を発見し、施策案を作ることは極めて有効であると確信しています。
施策立案時の注意点
施策立案では、まずは自由な発想でアイデアを広げる「発散」のフェーズが重要です。ブレインストーミングやKJ法などを活用し、多様な視点からアイデアを出します。その後、現実的な制約(予算、人員、時間)を踏まえて「収束」させ、実行可能な施策に絞り込みます。
また、この段階でも課題の認識が曖昧なまま施策を立ててしまうケースが多く見られます。また、発散の段階での自由な発想が抑制され、「前例踏襲」や「上司の意向」に引きずられることもあります。施策立案は創造性と現実性の両立が求められる難しいプロセスであり、発散」と「収束」のバランスが重要で、十分な時間と対話をかける必要があります。
施策の評価と優先順位付け(限られた資源の最適配分)
複数の施策案が出揃ったら、それぞれを評価し、実行の優先順位を決める必要があります。評価の項目としては、以下のようなものが考えられます。
1)インパクト(効果の大きさ)
2)実現可能性(コスト、時間、技術、人材の観点)
3)緊急性(早急に対応すべきか)
4)リスク(失敗した場合の影響)
これらをマトリクスやスコアリングで可視化することができますが、現実的には、会社の理念や上司の判断で施策が選択されることが多いようです。選択の差は、主にリスクに対する考え方の差が強く影響します。
なお、施策の優先順位は、現場の実行力や経営層の意向、顧客の期待など、複数の利害関係者の視点を踏まえて決定する必要があります。特に、実行部隊の納得感がないままに施策を押し付けると、実行段階での抵抗や形骸化を招きます。
この段階でも、施策を「思いついた順」「声の大きい人の意見」で決めてしまうと、効果の薄い施策にリソースを割いてしまうリスクがあります。評価と優先順位付けは、戦略的意思決定の要であり、冷静かつ論理的な判断が求められます。
施策の実行(現場との連携と柔軟な対応)
優先順位が決まったら、施策を実行に移します。この際には、以下のような実行計画の策定が重要です。
1)目的とKPIの明確化
2)担当者と役割分担の明確化
3)スケジュールとマイルストーンの設定
4)リスクと対応策の事前検討
実行は一度きりの「やりっぱなし」ではなく、Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Act(改善)のサイクルを意識し、柔軟に軌道修正を行うことが重要です。
実行段階では、現場の理解と協力が不可欠です。上からの指示だけでなく、現場の声を聞きながら進めることで、実行力が高まります。また、途中での状況変化に応じて、計画を見直す柔軟性も求められます。
実行結果の検証(成果と学びの可視化)
施策を実行した後は、必ずその成果を検証する必要があります。これは単なる「やったかどうか」の確認ではなく、「どの程度、目的に対して効果があったか」を定量的・定性的に評価するプロセスです。ここで重要なのは、事前に設定したKPI(重要業績評価指標)やKGI(最終目標指標)に基づいて、客観的に成果を測ることです。
たとえば、売上向上を目的とした施策であれば、売上高の変化だけでなく、客単価やリピート率、顧客満足度などの指標も併せて確認することで、施策の効果を多面的に評価できます。
成果の要因分析と学びの抽出
成果が出た場合も、出なかった場合も、その要因を分析することが重要です。成果が出た場合には「なぜうまくいったのか」を明確にし、他の領域への展開可能性を検討します。逆に、成果が出なかった場合には「どこに誤算があったのか」「仮説が間違っていたのか」「実行に問題があったのか」を振り返り、次の改善に活かします。
ナレッジの蓄積と共有
検証結果は、単に関係者内で共有するだけでなく、組織全体のナレッジとして蓄積し、今後の課題解決に活かすことが重要です。特に、失敗事例からの学びは貴重であり、属人化させずに組織知として共有する文化が求められます。
検証を「形式的な報告書作成」に終わらせてしまうと、せっかくの学びの機会が失われます。また、成果が出なかった場合に「責任追及」や「犯人探し」に陥ると、組織内に萎縮や忖度が生まれ、次の挑戦がしにくくなります。検証は「評価」ではなく「学びの機会」として位置づけることが、組織の持続的な成長にとって不可欠です。
広告
まとめ
会社や組織には、課題が溢れています。課題解決は、社員の仕事そのものであり、その能力が優れていることが、「出来る社員」「優秀な組織」と言えます。
課題解決のプロセスは、以下の5段階あります。
1)課題認識
2)施策の立案
3)施策の評価と優先順付け
4)施策実行
5)実行結果検証と修正
特に重要なのは1)課題認識、2)施策の立案、3)施策の評価と優先順位付けの3つの段階です。これらは、いわば「戦略フェーズ」にあたり、全体の方向性と質を決定づけます。
参考記事:ビジネスの問題解決は、「問題」と「課題」の違いと理解することから始まる









