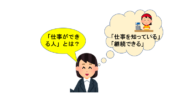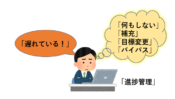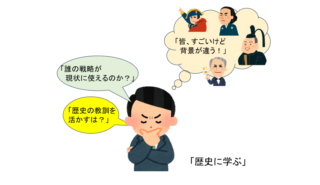「社畜すぎて草」「上司ガチャ爆死」等々、SNSへの会社不満投稿への対応策

「社畜すぎて草」「上司ガチャ爆死」等々、SNSへの会社不満投稿への対応策
「社畜すぎて草」「上司ガチャ爆死」「キャパい」って、何のこと?
「社畜すぎて草」
「上司ガチャ爆死」
「キャパい」
これらは、SNSの投稿で使われている言葉です。他にも「もう無理ゲー」「会社ガチャ外れ」「無限オブ限界」といった言葉もあります。いずれも、若手の社員が、会社や上司に対する不満から発せられたものです。他にもいろいろあり、以下にその意味と一緒にご紹介します。(すぐ、この種の言葉は陳腐化するので、2025年版とします)
・「社畜すぎて草」:自虐と笑いを交えた過重労働
・「上司ガチャ爆死」:上司との相性が最悪
・「会社ガチャ外れ」:就職先が期待外れだったという自虐的表現
・「もう無理ゲー」:理不尽な状況に対する諦めの感情
・「限界オブ限界」:限界を超えた限界。そこには、本音がにじむ
・「マイクロマネジメント地獄」:上司の過剰な管理に対する不満
・「評価されない芸人」:頑張っても認められない状況をネタ化した言葉。
・「メンタル削られる」:精神的ダメージが蓄積している状態
どうですか。「うまいこと言うものだ!」と感心します。
SNS上で、会社や上司に対する批判や不満を、皮肉を込めて言葉にしても問題が解決する訳ではありませんが、投稿した本人のストレス解消程度には役に立ちます。
この手の投稿は、不満の対象会社や個人の名前を出して批判・不満をぶつけるわけではありませんが、どの会社のことか、どの業界かは、関係者なら容易に想像できます。
批判や不満をぶつけられた会社や上司は、これらを無視していても、或いは気付かないでいても、投稿者が「社畜化」していくためか、次第に不満が薄くなり、投稿も忘れ去られていきます。
しかし、時として批判や不満はエスカレートし、離職が増える、職場のイメージが悪くなり採用に影響するといった実害が発生します。(いわゆる「炎上」)
会社で不祥事や事件があると、この種の投稿が劇的に増えます。普段、会社として気にしていないSNSの投稿に対して、神経質になり、なんらかの対応が迫られることになります。対応を誤ると、会社にとって大きな損害が生まれます。
私自身、所属している会社で不祥事があり、その関連の投稿で振り回されたことがあります。採用面接に来ていた学生から、
「御社では、○○のような噂があるとSNSで見ましたが、本当ですか?」
と質問されて、アタフタとしたことがありました。
SNS上の不満投稿に対して、会社(人事担当)がすべきポイントがあります。
1)定期的なモニタリング
2)SNSの投稿に対する感情分析
3)投稿に対する適切な対応
4)放置や否定はしない
SNS上の不満投稿は、「感情の可視化されたデータ」であり、会社としてはそれを観察・分析・活用することが必要と考えます。
広告

テキストマイニング入門 ExcelとKH Coderでわかるデータ分析
定期的なモニタリング
ネット上の投稿を定期的にモニタリングすることで、自社に関する批判・不満の傾向が把握できます。
例えば、X(旧Twitter)、TikTok、匿名掲示板(5ch、オープンチャット)などを対象に、「会社名」「業界名」「職種名」+ネガティブワード(「しんど」「詰んだ」「社畜」等)で検索します。また、投稿の頻度・語調・共感数(いいね)を分析することで、感情のトレンドが把握できます。
副次的な効果ですが、ネット上の投稿を見ると、若い世代が使う冒頭に挙げたような言葉があることを知ることができます。中高年の知らない言葉に出会い、驚きと新鮮さを感じると同時に、若者の気持ちに少しだけ近づくことができます。
SNSの投稿に対する感情分析
SNSの投稿は、感情の「兆し」として捉えることができます。投稿を読むと、それが自社や上司であることが想像できると、どうしても「会社側」人間として、反発が生まれます。
「何も分かってない奴が、何を言うか!」
「甘えたことを言うじゃねぇぞ!」
と言う気持ちを押さえて、投稿内容を冷静に分析することが大切です。ネット上には、有料、無料のSNS分析ツールが紹介されています。これらを使うと、「怒り」「悲しみ」「諦め」などの感情分類を行うことができます。或いは、文章を直接ChatGPTなどのAIで、感情分析させることも可能です。
また、特定部署や上司に関連する投稿が多い場合、構造的な問題の兆候と捉えるべきでしょう。実際、特性の名指しで批判されていた上司を調べると、その人のみならず、組織全体のパワハラ体質が明らかになったこともあります。
投稿に対する適切な対応
SNSに投稿された不満に対して、以下のような適切な対応が必要です。
1)「感情の声」を制度設計に反映する
「キャパい」「詰んだ」などの言葉が頻出する部署には、業務量の見える化と再配分が必要です。また、「上司ガチャ爆死」などの投稿がある場合、マネジメントの仕方を見直す、必要により社員研修を検討する必要があります。
2)社内風土の検証
実際の投稿(匿名化して)をもとに、
「この言葉の背景にある職場の空気は?」
と問題提起します。若手社員と管理職が対話する場を設け、価値観のすり合わせと共感形成を促進することです。
3)人事部門の役割
人事部門は、制度設計者であると同時に、感情の翻訳者と考えることもできます。SNS投稿を「愚痴」ではなく、「設計改善のヒント」として扱う視点が大切です。
あるIT企業の若手社員がX(旧Twitter)で
「社畜すぎて草。毎日終電、評価もされん!」
と投稿。社名は伏せていましたが、業界内で特定され、話題になったことがあります。
これに対して当該会社は、
① 社内ヒヤリングを実施して、「最近終電続きの部署はどこか」「評価制度に不満はないか」などを調査。
② その後、上司との面談を継続的に実施。
③ 業務量の見える化を実施して、仕事の再配分をしました。
これらを実施すると、その後なんと投稿者から
「会社が動いてくれた」
と再投稿があったとのこと。社内の心理的安全性が向上し、離職率が低下したとのことです。
放置や否定はしない
不満の投稿を放置したり、否定したりするのはリスクがあります。
例えば、否定的な対応は「言論封殺」と受け取られ、「炎上」して企業イメージを損ないます。また、感情が無視されると、若手は「ここでは成長できない」と感じ離職者が増える恐れがあります。
感情の声を無視すると、制度が現場と乖離し、形骸化します。
ある飲食チェーンの若手社員が
「上司ガチャ爆死。怒鳴られるだけで何も学べん」
と投稿したことがありました。その後、店名が特定され炎上。
企業は、即座に「事実無根」「名誉毀損の可能性あり」と内容を否定、社内掲示板で通達しました。その後、投稿者を特定し、厳重注意したのですが、本人は退職。公式アカウントで「指導体制に問題なし」と発信すると、さらに炎上。
こうした中、この企業に対して、「パワハラ隠蔽」「若手潰し企業」と批判が拡大。求人応募数が激減して、経営が困難になった例があります。
これは、感情の背景を探らず、企業防衛に走ったことに問題があったと考えられる例です。
広告
まとめ
「社畜すぎて草」「上司ガチャ爆死」といったSNS上の不満投稿に対して、会社(人事担当)がすべき4つのポイントがあります。
1)定期的なモニタリング
2)SNSの投稿に対する感情分析
3)投稿に対する適切な対応
4)放置や否定はしない
SNS上の不満投稿は、「感情の可視化されたデータ」であり、会社としてはそれを観察・分析・活用すること大切です。
参考記事:感性に訴える「共感提供ビジネス」を成功させる3つのポイント