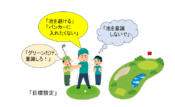「町のゴミ問題」をR・レッシングの「人の行動に関する4つの制約」から考えると

「町のゴミ問題」をR・レッシングの「人の行動に関する4つの制約」から考えると
R・レッシングの「人の行動に関する4つの制約」とは
夏の朝、自宅近くの公園に散歩にいくとゴミが散乱しています。ペットボトルやビールの空き缶、紙容器やお菓子の袋、吸殻といったものです。
「ゴミは持ち帰りましょう」
と書いた看板があるのですが、全く無力です。元々、公園内にはゴミ箱があったのですが、いつも溢れかえってしまうので、ゴミ箱を撤去して「ゴミは持ち帰りましょう」との看板を立てました。しかし、全く効果がありません。とはいっても、子供達は、ゴミを捨てることは少なく、むしろ問題はおとなの方のようです。
この看板は、人のマナーに期待したものでしたが、期待した行動を取ってもらえませんでした。場所によっては「ゴミの持ち帰り」が、うまく行っているところがあると聞いており、市や町内会は、どうしたものかと悩んでいるところです。
ところで、人間の行動は、単純に「本人の気持ち」や「損得勘定」によってのみ決まるわけではありません。米国の法学者のローレンス・レッシグは、その著書「CODE」に、人の行動に関し4つの制約要素があると論じています。
1)Norm(規範)
2)Law(法律)
3)Market(市場)
4)Architecture(構造)
この4つの要因を活用して、「制約」或いは「誘導」することができれば、人に望む行動をしてもらえることが期待できます。
これら4つの要因は相互に作用し合いながら、人々の意思決定に影響を与えます。冒頭に挙げた「ゴミを散らかさない」という行動やビジネス交渉において相手を動かすという行為も、この4つの要因から見ることで、より深い理解が得られます。
この記事では、それぞれの要因を解説し、町のゴミ問題とビジネス交渉の事例に照らし合わせながら具体的に考えます。
道徳(moral)による行動制限
道徳とは、人が「それをするのが良いこと」「それをしてはいけないこと」と内面的に信じている規範です。法律や罰則がなくても、人は「人に迷惑をかけたくない」「良心に従いたい」という理由で行動を律します。
問題になるのは、道徳が国や時代、宗教や周囲の環境などにより、各個人で異なることです。例えば、中国人は電車内や食堂などの場所で、大きな声で会話をしています。私自身の体験でも、普段公共の場では大きな声で会話をすることがないのですが、中国に出張すると公共の場でも大声で会話していることに気付くことがあります。
町のゴミ問題と道徳
町でゴミを散らかさないのは、多くの場合「人に迷惑をかけたくない」「きれいな環境を守りたい」という道徳的感覚から来ています。子供の頃に「ポイ捨ては悪いこと」と教えられた経験、地域での清掃活動に参加して「みんなで守る価値」を体験したことなどが、行動の基盤になっています。
残念ながら、「誰も見ていなければ」という状況では、道徳心が弱まり易く、例えば深夜に人通りの少ない道で、誰もいなければポイ捨てしてしまうといったことです。また、ゴミが全くない場所ではゴミを捨てない人が、既にゴミが散乱していると、罪悪感なくゴミを捨ててしまうということが起きます。
ビジネスにおける道徳
ビジネスの場においても、道徳は作用しています。例えば、「長年取引してきた相手を裏切らない」「相手が困っているときには助ける」という信義則に基づく行動です。法的拘束力はなくとも、取引先の信用を裏切らないことが、将来的な信頼関係を維持するための道徳的義務になっています。
ただし、ビジネスにおいては、道徳だけで企業の行動を制約することは難しく、利益と大きく反する状況では、「道徳より損得」が優先されるということになりがちになります。そんな場合、他の要因と組み合わせることが必要でしょう。
法律・ルール(law)による行動制限
法律やルールは、外部から強制される行動規範です。守らなければ罰金や刑罰、社会的制裁といった不利益が科されるため、人は従わざるを得ません。組織内にある規程、例えば業務規程や作業マニュアルも同様に人の行動を制限するルールです。
問題なのは、法律やルールがその時代や環境に合致しているかどうかです。法律やルールは、制定したときには、目的も合理性もあったのでしょうが、時とともに実情とは会わなくなってしまいます。すると勝手な解釈が生まれ、ルールを守らなくなるということが起きます。また、ルール違反をしても見逃されていると、誰もルールを守ることが無くなります。
町のゴミ問題と法律
ゴミを散らかすことは、多くの自治体で「軽犯罪」として罰則規定があります。あるいは「不法投棄禁止条例」によって取り締まることもできます。こうした法律の存在は、「ポイ捨てをすれば罰金を払う」という恐れを与え、人々の行動を抑制します。
ところが、実際に取り締まりが徹底されていないと抑止力とはなりません。監視がない場所では、ゴミの散乱が減ることはまずありません。
ビジネスにおける法律
ビジネス交渉では、契約書に基づく法律的拘束が大きな役割を果たします。納期の遅延や品質不良には賠償責任が発生します。相手が契約違反をした場合、訴訟や仲裁という手段で強制力を行使できます。
この法的拘束は、相手の行動を「最低限このラインまでは守らざるを得ない」という方向に動かす。だが法律はあくまで「下限」を決めるものであり、「より良い関係を築く」ことまでは保証していません。
市場・カネ(market)
市場による行動制約とは、「経済的なインセンティブ」による行動誘導のことです。得になるか損になるか、儲かるか損をするか、ということが判断基準です。
儒教的思想が強かった時代、「おカネで動くのは卑しい」といった考え方が強くありました。今でも、教員を「聖職者」とする考え方があり、勤務時間に見合う残業代を要求しても認められにくいといったことが報告されています。
町のゴミ問題と市場
ゴミを散らかさない行動を市場の力で動かす例としては、「デポジット制度」があります。ペットボトルに保証金を上乗せし、回収時に返金する仕組みは「お金が返ってくるから持ち帰る」というインセンティブがあります。また、ゴミをポイ捨てした場合に罰金を科すのも経済的動機付けの一つです。
この場合、道徳心が弱い人でも、「得になることならやろうか」と思う可能性が高まります。
ビジネスにおける市場
ビジネスにおいては、価格や利益配分が最大の行動駆動力です。ビジネスの相手を動かすには「これを選んだほうが経済的に得になる」という提案を提示するのが効果的です。例えば、「この部材を使えばコストを10%削減できます」「この条件を受け入れれば売上が伸びます」といった市場的インセンティブである。
ただし、市場だけで相手を動かそうとすると、競合他社との「値引き合戦」に陥りやすく、結果的に双方が疲弊するリスクがあります。これを避けるため、「長期的にみて利益になる」といくことが強調されます。
仕組み・アーキテクチャ(architecture)
仕組みとは、物理的・制度的な環境設計によって行動を自然に導くものを指します。法的強制や金銭的インセンティブがなくても、「そうせざるを得ない状況」を作ることで、人の行動を制約できます。ただし、仕組みを作るには、時間とおカネがかかることを覚悟しなくてはなりません。
町のゴミ問題と仕組み
町のゴミ問題に仕組みを活かす例は多くあります。たとえばゴミ箱を十分に設置することで「ポイ捨てするよりゴミ箱に捨てた方が楽」と感じさせる。あるいは公園のベンチや広場に「清掃中」の表示を出して常にきれいにしておけば、人は「きれいな場所を汚したくない」という心理を働かせるといったことです。
ただし、設置したゴミ箱の容量が小さかったり、ゴミの回収が滞ったりすれば、ゴミ箱のゴミが溢れ逆効果になることがあります。いっそゴミ箱を撤去し、「ゴミは持ち帰りましょう」と道徳心に訴える例もあります。対象者が、観光客やインバウンドの外国人であると、持ち帰る場所がなく、全く効果がないことが予想されます。
ビジネス交渉と仕組み
交渉の現場でも、仕組み設計は有効です。例えば「共同開発プロジェクトの枠組み」をつくり、取引先が自然に協力せざるを得ない環境を整える。「定期的な情報共有会議」や「共通プラットフォームでのデータ管理」も、相手を動かす仕組みといえます。
仕組みで相手を動かすことは、単にカネで誘導するよりも強力です。なぜなら、一度仕組みが回り始めると、個々の判断を超えて「そうするのが当然」という流れが生まれるからです。
まとめ
人の行動は、①道徳、②法律、③市場、④仕組みの4つの要因で方向づけられます。町のゴミ問題も、ビジネス交渉も、この4つの視点を組み合わせることでより深く理解でき、効果的な介入策を導き出すことが期待できます。
ただし、「人の行動を制約する4つの要因」は、単独で作用するのではなく、相互に補完し合います。
1)道徳は人々の内面的規範を支えるが、その道徳は人や状況によって違う
2)法律は最低限の強制力を持つが、監視が不十分だと形骸化する
3)市場は即効性があるが、短期的で価格競争に陥りやすい
4)仕組みは環境設計として持続性があるが、初期設計を誤ると逆効果になる
これらを考慮して、人の行動を誘導する方法を見いだすことが大切です。
参考記事:誰でもするミス、避けられない人間の2種類の「行動ミス」と3つの対策
「人に迷惑をかけなければ何をしても良い」をマナーとエチケットから考える