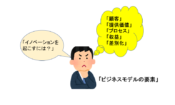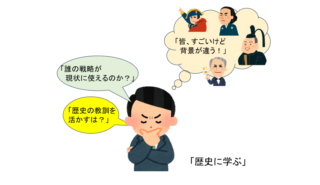価格交渉で使われる3つの価格、「外的参照価格」「実売価格」「内的参照価格」

価格交渉で使われる3つの価格、「外的参照価格」「実売価格」「内的参照価格」
「外的参照価格」「実売価格」「内的参照価格」とは
「この価格で買ってもらえるか?」
「これなら売れるが、利益がでない!」
価格を決めることは、商売の基本ですが、案外難しいものです。営業マンと購買担当が、直接価格交渉をする場合は、更に難しくプレシャーが掛かるものです。
よく、アンカー効果を狙って、まず売り手が高い価格を提示する。或いは、買い手がとてつもなく安い価格を出す。そんなトランプ大統領が好きそうな取引方法もありますが、双方に売らなければならない事情、買わなければならない事情があると、落ち着くところに落ち着きます。(どちらかに、多少不満が残るかも知れませんが。)このプロセスを価格という視点からみると価格交渉にもパターンがあります。
以下に、スーパーでの買い物の例をご紹介します。
ある普段買い物をしない男性が、奥さんに頼まれて味醂を買いに行きました。
「定価より2割も安くて、1本780円で買ってきた」
そう奥さんに報告すると、
「あの店、2割引が当たり前なのよ。私なら1本700円以下でないと買わないわ」
「そうか。700円切れを待っていて買えずに、今日になって味醂が無くなっていたのか」
これは、商品の値段が高いか安いかを判断するのに、3つの基準となる価格(「参照価格」)があることを示しています。
3つの「価格」とは、
1)外的参照価格:定価、メーカー希望価格
2)実売価格:実際に売られている価格
3)内的参照価格:消費者の認知している価格
です。
外的参照価格は、「定価」としてパッケージやカタログ等に書いてあり、誰でも分かります。実売価格は、日頃の買い物や口コミ、ネットやチラシで調べたりすることができる実際に売られている価格です。冒頭の例では、奥さんは日常の買い物を通して、味醂の実売価格を良く知っています。内的参照価格は、購入しようしている商品に対する「妥当な価格」で、「これなら買う」という価格です。この奥さんの場合、それは700円でした。旦那には、明確な味醂の内的参照価格がなく、「2割引なら買う」という内的参照価格(割引率)で買ったということです。
内的参照価格は、購入の決断に大きな影響を与えます。消費者は、内的参照価格の上か下かの、わずかな差でも敏感に反応して、「買う」「買わない」の判断をします。一方、販売する方は、相手の内的参照価格を把握することが重要です。相手の内的参照価格を掴み、それ以下の価格を提示できるかということです。また、様々な方法で、相手の内的参照価格を引き上げようともします。アンカー効果を狙って、始めに高い値段を「吹っ掛ける」のは、相手の内的参照価格を上げようとするものです。このあたりのやり取りが、セールスの面白みであり、難しさでもあります。
この記事では、車を実際に購入した例を通して、この3つの価格をご紹介します。
車種選びを「精緻化(せいちか)見込みモデル」で考える
消費者が商品を購入する際、その機能など実用性を重視して選ぶ場合と、「それが好き」「皆が持っている」といったことに引かれて選ぶといったことがあります。
この二つの選択ルートについて、「精緻化(せいちか)見込みモデル」と言われるものがあります。
精緻化見込みモデルとは、人々が説得的コミュニケーションにどのように反応するか、つまり態度変化に至る過程を説明する心理学的なモデルです。具体的には、人は説得メッセージの内容を深く吟味する「中心ルート」と、メッセージの周辺的な要素(発信者の信頼性、感情的な印象など)で判断する「周辺ルート」の2つのルートを通じて態度変化を起こすとされています。
中心ルートでは、説得メッセージの内容、根拠、論理性をじっくりと分析し、その内容を評価して態度変化に至るルートです。関与度や知識が高い人がこのルートをたどる傾向があります。ものを買うときは、性能やコスパなど実用性で判断するルートです。
周辺ルートでは、メッセージの周辺的な要素(発信者の信頼性、感情的な印象、広告のイメージなど)で態度を決めていくルートです。関与度や知識が低い人がこのルートをたどる傾向があります。最近は、どの商品も一定の性能や品質をもっていて、購買のメインが、周辺ルートになることが多くなっています。
消費者が、どのルートを通って商品を購入するかは、その人によりますが、人によっても商品毎に異なるルートを選ぶこともあります。
65歳越え夫婦の車種選びの例
65歳越えの夫婦が、15万キロ以上走った車を乗り換えようと考えました。これまで、セダンやミニバンなどに乗ってきましたが、夫婦二人の年金暮らし、旅行や買い物に「ちょうどいい車」が欲しいし、高齢ドライバーでも安全に運転できるといった基準で車種選びを始めました。
この場合は、明らかに中心ルートです。なぜなら。「自分たちの生活に合う車を理性的に探している」「メリット・デメリットを丁寧に検討している」「感情や見た目よりも実利を重視している」といったことがわるからです。
夫婦は、ディーラーに出向き、営業マンに相談しました。すると、ステーションワゴンを勧められました。その理由は、以下のようなものでした。
1)コスパ:「ステーションワゴンはSUVより安く、燃費も良いです」「ハイブリットなのでなおさら」
2)安全性:「自動ブレーキ、死角警告など最新の安全装備があります」
3)広さ:「リアシートを倒せばゴルフバッグや旅行の荷物も多く積めます」
4)車体のサイズ:「大きすぎず、街乗りも楽。駐車も安心」
こんな理詰めの説得で、夫婦はステーションワゴンに決めました。周辺ルートとして、「ベンツを運転したい」とか、「ワゴンは、平凡なスタイルしかない」といった感情から、車種を選択することもできましたが、安全と使いやすさやコスパについての説得が決めてとなってステーションワゴンということになりました。
展示車の前に、
「『もう大きな車はいらない。でも軽では物足りない』そんな声に応える1台です。」
と書かれた言葉は、ステーションワゴンを選ばせるにふさわしいフレーズだと思えました。
ちなみに、横のSUVには
「個性と自由を大切にする人のための車」
とありました。周辺ルートで車選びをする人達の為のフレーズです。
車の価格交渉における3つの価格
車種が決まって、いよいよ価格交渉です。勿論、価格によっては「買わない」という選択の余地があります。どのように価格が決まったか、そのとき3つの価格がどう使われたかを再現してみます。
車の価格をめぐる攻防戦
定年退職して数年が経過した年金生活を送る二人とも65歳を超えた夫婦は、長年乗っていた愛車がいよいよ限界を迎えたのを機に、思い切って新車のステーションワゴンを購入することに決めました。
「これが最後の車になるかもしれないな」
そう思ったご主人のAさんに妻も
「せっかくだから、少し高くて安全な車がいいわ」
と同意。候補に上がったのは、メーカー希望価格350万円の最新型ハイブリッドのステーションワゴンに決めました。
試乗も終えて、いよいよ若い営業マンのTさんと価格交渉です。一通りカタログと値段表をみて、Aさんは、
「この車、気に入ったよ。けどね、年金暮らしでね。300万以下ならすぐ買うけどな。なにも無理は言ってないですよね」
営業マンのTさんは内心ドキッとする。(300万…?さすがにそれは…)
「値引きといっても、20〜25万円程度なんです。ただ…いま、ちょうど決算月でして…!」
Tさんは、店長に掛け合うためにその場から離れました。
しばらくして、Tさんが戻ってくると、
「店長と相談したのですが…今回、値引きは30万円までが限界です。つまり、320万円です。ですが、フロアマットにETC、3年間分のオイル交換と撥水コートサービスをつけます。」
Aさんは、じっと腕をくんで黙っています。そのとき、奥さんがAさんに
「ねえ、あとちょっとだけ下がったら、いいのにねえ…」
と小声でつぶやきました。営業マンのTさんは、ここが正念場と、
「……わかりました。最終判断は店長に任せるということで、ダメもとで、最後のお願いしてきます!」
と発言、ふたたび席を離れました。そして、数分後
「お待たせしました。店長の特別判断で、315万円でどうでしょうか? もう本当にこれが限界で…!」
Aさんは、しばし無言でしたが、
「よし、それなら買おう」
ということで、Tさんは、ステーションワゴンの契約を結ぶことができました。
帰り道、妻のBさんが、Aさんに
「あなた、最初から315万位を狙っていたのでしょ?」
「300万は、ハッタリだが、本気でもあったよ。ただ、必死で店長と交渉する営業マンをみていて、310万は仕方ないかなとは思ったよ。粘ったお陰で、いい買い物ができた。」
3つの価格と価格交渉
以上は、昨年私が買ったトヨタカローラツーリングの値段交渉の実話です。
この話には、「外的参照価格」「実売価格」「内的参照価格」という3つの価格概念を当てはめることができます。
外的参照価格として、メーカー希望価格の350万円がありました。正直「こんなに高いのか」という印象です。
これに対して、Aさんは、雑誌や友人の話から「標準的な値引きは20〜25万円」という情報を得ており、325万〜330万円という「実売価格」がありました。
Aさんの「300万円以下ならすぐ買う」というのは、 内的参照価格(消費者の心の中の価格基準)です。本心は、310万円位だったのですが。
そこで、営業マンのTさんは、店長に掛け合うことで出した320万円で「値下げの限界感」を演出しました。これに対して、Aさんの「お買い得感」である300万円が、揺らいできて内的参照価格が引き上げられます。
Tさんは、最初の限界線である320万円から、「アクセサリーを付ける」「店長決裁で315万円」を示すことで、交渉成立点を見つけ出すことができました。
この駆け引きでは、ディーラー側は、「外的参照価格」(雑誌や定価)と「提示価格」の差で、お得感を演出しました。消費者側は、「内的参照価格(300万)」より高いかどうかで意思決定を迷いましたが、結局、「外的参照価格よりはかなり安いし、雑誌の情報よりも安い」「アクセサリーも付いている」という相対的お得感で、内的参照価格を上方修正し、315万円を受け入れたということです。
まとめ
商品の値段が高いか安いかを判断するのに、3つの基準となる価格(「参照価格」)があります。それは、
1)外的参照価格:定価、メーカー希望価格
2)実売価格:実際に売られている価格
3)内的参照価格:消費者の認知している価格
です。売値を決めたり、直接価格交渉したりする際、これらの価格を意識することが重要です。