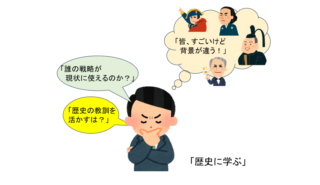「上司が嫌だ」と思う理由は、部下自身の立ち位置によって異なる

「上司が嫌だ」と思う理由は、部下自身の立ち位置によって異なる
「上司が嫌だ」と思われるのはなぜか?
「上司が嫌」
「上司は苦手」
自分の上司に対して、こんなネガティブな感情を持つ人は、少なくありません。Job総研の「2022年 職場の上司に関する調査」によれば、アンケートに答えた全体の60.4%が「苦手な上司がいる」と回答しています。その理由として「高圧的で偉そう」(50.4%)「責任転嫁をしてくる」(24.1%)「明らかに能力がない」(23.4%)「部下の粗捜しばかりしている」(23.0%)という結果です。
上司と部下の関係は、成果を左右する重要な要素でありながら、必ずしも「円滑」ではなく、少なからず上司への不満があるものです。上司への不満の原因として、アンケート結果にあるように「上司の性格」「上司が無責任」「上司の能力」といったことが挙げられます。しかし、実際はこれほど単純ではなく、部下自身の立ち位置、つまり能力や意欲の違いにも深く関係しています。
例えば、能力の高い部下にとっては、あれこれ「ちょっかい」を出してくる上司は「嫌」です。一方、新人など仕事に不慣れな部下からみると、「かまってくれない」上司は、「嫌」と感じるでしょう。
ところで、どんな組織にも「2:6:2の法則」といわれるパレートの法則から派生した法則があります。集団には、優秀な上位人材が2割、平均的な中位人材が6割、下位グループが2割に分かれるという考え方です。
よく例に出されるのが、働きアリの集団です。働きアリのうち、積極的に働くのは2割だけで、6割は普通に働き、残りの2割は働かないというのです。
この「2:6:2の法則」を職場の人材に当てはめると以下のようになります。
1)上位2割「できる部下」:成績優秀で意欲も高く、自律的に働ける部下
2)中間6割「普通の部下」:平均的な能力と意欲を持ち、上司の支援によって成果が変動する層
3)下位2割「困った部下」:業績や理解力が不足しており、サポートが必要な部下
この層ごとに「上司に対する不満の理由」は異なります。冒頭に紹介したアンケート結果は、各層を一緒にした回答結果と推定できます。
この記事では、階層毎に「上司に対する不満の理由」と対処法をご紹介します。
上位2割の「できる部下」が上司を嫌がる理由
1)指図が多過ぎる
上位層に位置する部下は、仕事の全体像を把握し、問題解決能力も高いため、自らの裁量で動きたいという欲求が強くあります。そのため、上司からの過度な指示や細かい介入に対して「信頼されていない」「無駄な口出しだ」と感じ、ストレスを溜めがちです。
特に、自分のペースややり方で仕事を進めたいタイプにとって、逐一の指示出しや進捗確認は「能力を疑われている」と映り、上司に対して敵意や失望感を持つ原因となります。
2)評価に対する不満
できる部下は、自らの努力と成果に対して正当な評価を求めます。しかし、上司が評価を言葉に出さなかったり、成果を「当然」と受け止めたりすると、部下は不満を抱きます。褒められたいわけではないでしょうが、「見てくれているかどうか」が重要です。
3)「上司が自分より劣っているように見える」
部下の方がスキルや知識があるとき、上司が自己保身や権威に固執していると、優秀な部下はその上司に対し尊敬できず、表面上は従っていても内心で「嫌だ」と感じます。特に、自分の意見を退けられたり、非論理的な指示をされたりしたときに不満が強まります。
中間6割の「普通の部下」が上司を嫌がる理由
1)指示が曖昧で、どう動いてよいかわからない
中間層は、上司の支援や方向付けがあれば高い成果を出せる可能性を秘めています。ところが、上司が「放任型」「丸投げ型」であったり、具体的な行動指示や優先順位の提示が不十分だったりすると、混乱や不安を招きます。
このような部下は「何をすれば評価されるのか」「自分の仕事が合っているのか」が分からなくなり、次第に上司への不信感を募らせます。
2)忙しそうで話しかけづらい
中間層の部下にとって、上司は困ったときに助けてくれる存在であることが理想です。しかし、上司が常に多忙で、相談するタイミングがつかめない、もしくは相談しても「後にしてくれ」と言われるような状態が続くと、部下は孤立感を覚えます。
これにより「うちの上司は頼れない」「上司としての役割を果たしていない」と感じ、心理的な距離が生まれ易くなります。
3)一貫性がない
あるときは厳しく、あるときは放任といったように、態度や評価基準がコロコロ変わる上司に対して、部下は強いストレスを感じます。中間層の部下ほど、ルールや指針を必要としているため、上司の「気まぐれさ」や「曖昧な言動」は混乱の元になります。
下位2割の「困った部下」が上司を嫌がる理由
1)面倒を見てくれない
下位層の部下は、業務遂行能力や習熟スピードが低いため、本来であれば手厚いフォローが必要です。しかし、上司がそれを面倒に思ったり、「何度言ってもできないやつだ」と見切ったりすると、部下は見捨てられたと感じます。
「どうせ自分には期待していないのだろう」「言っても無駄と思われている」と感じた部下は、上司に対して無力感や恨みを抱くようになります。
2)責められるばかりで、成長のヒントがない
出来の悪い部下ほど失敗が多く、叱責されやすい立場にありますが、そこに「どうすれば良くなるか」という建設的なフィードバックがなければ、ただの罰としか受け止められません。
上司が感情的に怒鳴る、人格を否定するような叱責をする、あるいは放置することにより、部下は次第に自己肯定感を失い、仕事に対する意欲も減退します。そして最終的には、「この上司のもとではやっていけない」と強く感じるようになります。
3)ミスを許してくれない
能力の低い部下ほどミスは避けられません。しかし、上司が「またか」と呆れたり、「もう教えたはず」と突き放したりすることで、部下は「自分はダメな人間」と感じてしまいます。
ミスに対する許容や、成長を信じる姿勢がないと、部下は「見捨てられた」「責められてばかり」と感じ、上司との信頼関係が築けません。
上司が取るべき対応
上司が部下一人ひとりの感じ方を理解せず、「全員に同じように接する」だけでは、必ず不満が生まれます。上司には以下のようなスキルと視点が求められます。
1)相手に応じたマネジメント
・できる部下には「裁量を与える・尊重する」
・中間層には「目的とやるべきことを明確にし、節目ごとに支援」
・下位層には「繰り返し丁寧に教え、努力を認める」
2)信頼の可視化
評価は、言葉や行動で「見える化」しない限り伝わりません。感謝・評価・フィードバックをタイムリー行うことで、信頼関係を築くことが重要。
3)傾聴と対話
部下の「嫌だ」という感情の背景には、何らかのニーズがあるはずです。対話を通じて本音を引き出し、それに対応することが、誤解を解消し関係修復に繋がります。
まとめ
「上司が嫌だ」と感じる理由は、部下の能力や立場によって異なります。優秀な部下には「信頼されていない」と映り、平均的な部下には「わかりにくい・頼れない」と感じられ、不得手な部下には「見捨てられている」と思われがちです。
上司として重要なのは、自分の基準で一律に接するのではなく、部下それぞれの立ち位置を見極めて、最適な関わり方を選ぶことが重要です。
参考記事:リーダーシップ能力の他に必要な日本の「出来る上司」の能力とは?
「理想の上司」とは、「部下を成長させ幸福にしてくれる人」のこと