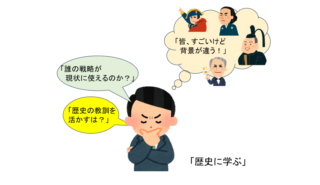採用担当の嘆き「採用したい人材がいない」という理由とは?

採用担当の嘆き「採用したい人材がいない」という理由とは?
「採用したい人材がいない」のはなぜ?
最近の就職戦線は、採用数と就活生を単純に比較すれば、学生優位の売り手市場です。ところが、
「希望する職種、希望する会社の内定が取れない」
という就活生が多くいる一方で、学生に超人気の企業を除けば、
「採用したい人材がいない」
と嘆く企業の採用担当者だらけです。
「人はいるけど人材がいない」
なんて声も聞きます。
こんなミスマッチが起きるのは、採用する企業に明解な採用人材像がないことが原因の一つです。各企業は、学生に将来「会社幹部」となることを期待し、学力(学歴)に加え、コミュニケーション力、リーダーシップなど「総花的な人物」を求めます。たとえ技術系の学生であっても、専門技術そのものより、将来的に「幹部」となれるポテンシャルがあることを重視する傾向があります。
就活生は、それが分かっていますから、エントリーシートや面接において、自分が「リーダーになれる人材」であることをアピールします。しかし、残念ながら就活生全員がリーダータイプではありません。「リーダーシップ」をアピールしても、百戦錬磨の面接官は、それが本物かどうかを容易に見抜きます。
その結果、多くの就活生が「希望する会社の内定」がもらえない。多くの会社で「期待できる人材」が採用できないということになっています。
問題は、企業が採用するすべての人がリーダーの役割を担うわけでもないのに「リーダーになれる優秀な人材」を求めるところにあります。これに合わせて、就活生も自分を「企業が期待する優秀な人材」に見せようとします。しかし、そもそも「優秀な人材」とは、どんな人物なのかが、企業も就活生も曖昧なのではないでしょうか。
私は、
「人材の価値は、チーム(社会)のピースを埋めることができるかどうかで決まる」
と考えます。日本企業の採用活動では、優秀な人材として、「リーダーになれる人材」「万能型人材」を選抜しようとする傾向があります。プロ野球のドラフトで、「エース投手候補」「4番打者候補」ばかりを指名するようなものです。全選手にそんなことを期待しても無理なことですし、実現できたとしても、それで本当に強いチームができるとは限りません。
組織において、全員がリーダーになる必要もなく、目立つ成果を上げることだけが人材としての価値ではありません。むしろ、目立たない仕事であっても、それがチームの全体最適を支えている限り、かけがえのない仕事です。目立つ仕事、目立たない仕事、大きな役目、小さな役目、これらのピースをぴったりと埋めることができる人材こそが、「優秀な人材」と考えます。小さなピースに、これを上回る人材をあてはめれば、「優秀な人材」とは言い難いことになります。まさに「役不足」ということです。
日本企業の学卒者採用活動において、ミスマッチが起きる原因には、以下のようなものがあります。
1)一括採用の弊害
2)「総合職」という曖昧な職種
3)人事制度変革を阻む風土
これらの要因で、就活生が希望の職を得られない。企業が、満足する学生を採用できない。せっかく採用しても、すぐ離職してしまうといったことが起きています。
この記事では、企業の採用方法や人事制度について、私の米国経験を例として考えます。
一括採用の弊害
日本企業の採用は、「将来のリーダー候補」を前提としたポテンシャル採用が主流です。特に大企業では、新卒一括採用という制度により、職務内容に合った専門性よりも、「ゼネラリストとして育てられる素地」が重視されます。裏を返せば、「会社のどこにでも配属できる汎用的な優秀人材」を求めているということです。根底には、とりあえず「優秀な人材を多く確保し、後で配属を考えればいい」という戦術があります。一括採用においては、他社よりも、より多くの人数を確保することが優先され、社内の人材ニーズとは必ずしもマッチングしません。
「将来のリーダー候補」を前提とした採用では、例えば「現場で一生懸命に働きたい人」や「裏方として組織を支えたい人」といった専門性や安定性を志向する人材は、過小評価されます。採用後、本人の適性を無視したジョブローテーションも珍しくなく、結果的にモチベーションの低下や早期離職を引き起こします。
「総合職」という曖昧な職種
採用活動において、大卒以上の学歴を持つ人の多くは、「総合職」に応募します。
「総合職」とは、企業の中核を担う幹部候補として、将来的に管理職になることを期待される職種です。幅広い業務を経験し、組織全体のことを理解することが求められます。採用に当たって、企業が「リーダーシップ」を期待できる人材を求めるのは、総合職が将来の企業幹部になるルートであるからです。
ところが、実際が総合職として採用されても、管理職になるのは年功序列という慣習があり、順調に昇進した場合でも、大企業では10年から15年という期間を要します。
実際、中央省庁や大企業が、「リーダーになれる人材」を総ざらいで採用しても、新人には長い期間リーダーとしての仕事などほとんど廻ってきません。人材のムダ使いとでもいうような現象が起きています。昔の新入社員なら、我慢して務めたのでしょうが、今は簡単に離職してしまいます。
「総合職」といった曖昧なカテゴリーではなく、「会社のピースを埋めること」を主眼として募集ができないかと思います。たとえば、「経営者募集」「管理職募集」「高度エンジニア募集」「営業職募集」といったように。制約が多そうですが、「採用後に適性によって職種の変更が可能なこと」を付け加えておけばいい話です。
米国における職種別採用の例
米国において、会社の幹部として会社を立ち上げる際、50人ほどの社員を募集した経験があります。このとき従業員を採用するにあたり、中途新卒に関係なく、「部長級」「課長級」「係長級」「一般」というカテゴリーで従業員を募集しました。すると、「部長級」や「課長級」でも、新卒者が応募してきました。これらのカテゴリーは、「一般」より高い給料が出ます。実際に選考した結果、新卒で「課長級」に採用された者もいました。また、面接の中で、
「『課長級』は無理だが、『係長級』からスタートしては」
と本人と会話し採用した者もいました。その後、ポジションが空くと社内外に対して、公募し選考して充足しています。残念ながら「部長級」ポジションは、4つしかありませんので、能力があっても部長になれない人はいます。幸い米国は転職の機会も多く、他にそれなりのポジションを見つけて移っていきます。一方、20年以上も本人の希望で、一般職に留まり続けて満足している人もいます。
人事制度変革を阻む風土
年功序列型の人事制度。「大卒=総合職」という採用の慣習。それらに問題が多いことは、採用や人事に係る人の間で共有されつつあります。しかし、実際に制度を変えることは容易ではありません。
人事担当者が年功序列制度の見直し、人事制度の改革を提案しても、これまでの制度で出世してきた人や今後ポジションが回ってきそうな人達の反発が予想されます。また、
「若い時は、苦労して当たり前」
といった考え方が根強くあります。結局、人事や採用制度を見直すことができるのは、企業トップだけです。ところが、そのトップも日本ではオーナー社長でない限り、これまでの制度で出世しトップになった人です。ルールを変える決断が容易でないことは、想像に難くありません。
人事制度の改革には、「社外の意見」、「株主の意見」なども活用して、トップが責任を取る形で進めることが必要ではないでしょうか。
まとめ
日本企業の学卒者採用活動において、
1)一括採用の弊害、
2)「総合職」という曖昧な職種、
3)人事制度変革を阻む風土、
によって、就活生が希望の職を得られない。企業が、満足する学生を採用できないといったミスマッチが起き、せっかく採用しても、すぐ離職してしまうといったことが起きている。採用制度や人事制度改革には、企業トップのリーダーシップが期待される。
参考記事:オンライン採用になって、中小企業が益々苦戦する理由と対策
「本当に欲しい学生」を採用するために採用担当と面接官がすべき5つの事柄