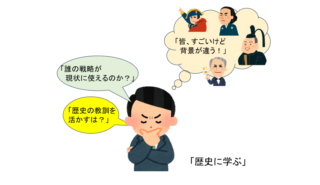自己研鑽・習いごと・ダイエットを途中でやめないための心理的・行動的対策

自己研鑽・習いごと・ダイエットを途中でやめないための心理的・行動的対策
なぜ、途中でやめてしまうのか、その心理的理由
「英語を勉強し直そうと教材を揃えたけど続かない」
「楽器を買って習い始めたがやめてしまった」
「ダイエットを始めたが1か月で挫折」
こんな風に、自己研鑽・習いごと・ダイエットなど「頑張ってみよう」と始めても、途中でやめてしまったという経験はありませんか。個人の成長や変化を目指す取り組みは、始めることよりも「続けること」の方が難しいものです。多くの人が「三日坊主」を経験します。これは、意志が弱いからではなく、人間の心理構造に原因があります。
人の脳は、変化を嫌い、現状維持を好むようにできています。脳科学では「恒常性(ホメオスタシス)」という仕組みがあり、日々の生活リズムや行動パターンを変えると、脳がストレス反応を起こします。そのため、最初のうちは新しいことを続けるのが苦しく感じられ、やめる方向へと引き戻されてしまうのです。
また、成果がすぐに見えにくい活動(ダイエットや語学学習など)は、報酬が遅れてやってくる「遅延報酬型」です。このタイプの行動は、短期的快楽を求める人間の本能に逆らうため、モチベーションが維持しにくくなります。
三日坊主から逃れる方法には、いくつかあります。
1)楽しみを見つける
2)寄り添う人を見つける
3)記録を付ける
ということが有効です。更に補助的に
4)小さな成功を積み上げる
5)環境を整える
6)意味づけを再確認する
といったことがあります。
これらは、一種の仕組みです。「継続できない」とき、「意志の弱さ」として、自分を責めるのではなく、「継続する仕組み」を作りあげることが重要です。
広告

200万人の「挫折」と「成功」のデータからわかった 継続する技術
楽しみを見つける
人は「楽しい」と感じるとき、脳内にドーパミンが分泌されます。ドーパミンは「やる気ホルモン」と呼ばれ、行動のエネルギー源となります。したがって、どんな活動も、そこに「楽しさ」を見出せるかどうかが継続の分かれ道になります。
たとえば、英語学習を続けたいと思っても、「TOEICで何点取る」といった目標だけでは息が詰まります。代わりに、「好きな映画を字幕なしで観たい」「海外のYouTubeを理解したい」など、感情に訴える目標を設定すると、勉強が「義務」から「遊び」に変わります。楽しみを伴う学習は、自然と継続可能になります。
ダイエットでも同じです。単に「体重を減らす」ことを目的にすると、食事制限や運動が苦痛に感じられ、反動が起こります。しかし、「おしゃれを楽しみたい」「体が軽くなって旅行をもっと楽しみたい」という前向きな動機に変えると、行動に意味が生まれます。
また、エクササイズを「ゲーム化」するのも効果的です。スマートウォッチで歩数を競う、ダンス動画を真似る、音楽に合わせてトレーニングするなど、「楽しみながら達成感を得る」仕掛けを入れると、脳がポジティブな刺激を得て、習慣化が進みます。
寄り添う人を見つける
人は社会的動物であり、孤独な努力よりも、他者と関わりながら行う行動の方が持続しやすいものです。心理学では「社会的支援(ソーシャルサポート)」という概念があり、これは他者からの共感・励まし・評価・相談がストレスを軽減し、目標達成を後押しするというものです。
「伴走者」の存在は、絶大な効果を発揮します。個人的には、「伴走」が継続性には最も効果があるのではと思っています。
例えば、
「結果をコミットする」
とPRするライザップは、特別なダイエットプログラムを使っているわけではありません。しかし、インストラクターが密着して結果が出るまで「伴走」してくれることで、継続率が高く、結果として「結果」がでるのです。
小中学生が、学習塾に行って成績が上がる最大の理由は、塾に行って先生がそこにいるということで、遊びたい気持ちやスマホをいじりたい気持ちを押さえて、勉強に集中するからです。
他には、ランニングを始めても三日坊主になる人が、友人と一緒に走るようになると、継続率が飛躍的に上がります。「今日は雨だからやめよう」と思っても、相手との約束があると走り出す気になります。これは「外発的動機づけ」がうまく働いている例です。
記録を付ける
続けるための第三の柱が「記録」です。記録を付ける行為には、自己観察・達成感・反省という三つの効果があります。
まず、記録によって自分の行動が可視化されると、脳は「継続の実感」を得ます。ダイエットで体重を毎日グラフにすると、数値が上下しながらも少しずつ下がっていくのが見え、「自分は変われている」という自己効力感が生まれます。
この「見える化」は非常に強力で、自己研鑽においても有効です。勉強時間をアプリで管理したり、日報形式で「今日できたこと」「気づいたこと」を記録したりするだけで、自分の成長を客観視できるようになります。
さらに、記録は「やめたくなった時の歯止め」になります。人間は「積み上げたものを壊したくない」という損失回避の心理を持っています。たとえば、ランニングアプリで「30日連続達成」と表示されていれば、途切れさせたくないという感情が働き、行動を継続させます。
また、後から振り返ることで「どの時期に停滞していたか」「何がきっかけで再び進んだか」を分析でき、次の計画に活かせます。これは「メタ認知的学習法」にも通じる重要なステップです。
小さな成功を積み上げる
途中でやめてしまう大きな理由のひとつは、「目標が高過ぎて達成感を得られない」ことです。例えば「半年で10kg減量」や「英検1級取得」などは、長期的で抽象的な目標です。脳はすぐに報酬を得られない行動を続けるのが苦手なため、途中で挫折してしまいます。
そこで有効なのが、「スモールステップ法」です。これは、大きな目標を小さく分割し、短期間で達成できる目標を積み重ねる方法です。ダイエットであれば「まずは1週間、間食を減らす」「3日連続で歩く」といった単位で設定します。
これにより、小さな成功体験が積み上がり、自己効力感が増します。心理学者バンデューラの研究によれば、自己効力感(自分はできるという感覚)が高い人ほど、行動を長く続ける傾向があります。小さな成功の繰り返しが「やればできる」という信念を育て、行動のエネルギーになります。
環境を整える
続けるためのもう一つの重要な視点が、「環境のデザイン」です。意志の力だけに頼るのではなく、やらざるを得ない環境を作ることが、実は最も現実的な方法です。
例えば、英語の勉強を朝にしたいなら、寝る前に机の上に教材を開いておく。ランニングをしたいなら、玄関にシューズを出しておく。これらは「行動の摩擦」を減らす方法であり、習慣化の初期段階では特に有効です。
また、スマホやテレビなど誘惑を遠ざける「逆環境設計」も効果があります。SNSを見ると他人と比較してやる気を失う人は、アプリの通知を切るだけでも集中力が保てます。
環境を整えることは「行動経済学」でいう「ナッジ」の考え方にも通じます。行動を強制するのではなく、自然と正しい方向に導く仕組みを作ることが、継続への近道です。
意味づけを再確認する
途中でやめてしまう人の多くは、そもそも「なぜそれをやるのか」という目的があいまいになっていることが多いです。
人間は、外的報酬(お金、称賛、資格)だけでは長期的なモチベーションを維持できません。内的動機づけ、すなわち「自分がどうなりたいのか」「なぜそれをしたいのか」という個人的意味が明確なときにこそ、行動は持続します。
例えば、資格取得のための勉強も、「昇進のため」だけでは続きにくいものです。「専門知識を身につけて、今の仕事の質を上げる・顧客に貢献したい」という思いがあると継続しやすくなります。
ダイエットも「他人に良く見られたい」より、「健康的に歳を重ねたい」という内面的理由の方が、持続力が高いといわれます。
心理学的には、人は「自律性」「有能感」「関係性」が満たされるときに最もモチベーションが高まるとされます。自分の行動が自分で選んだものであり、他者との関係や成長につながっていると感じられるように意味づけを見直すことが、継続の鍵です。
なお、「続かない」ことに関して、「意味付け」の視点でみた内容は、参考記事をご覧ください。
参考記事:「学び」が続かない3つの理由と「重要でも緊急性がない」ことを後回しにしがちなとの同じ
広告
まとめ
自己研鑽・習いごと・ダイエットなどを途中でやめないためには、以下のようなポイントがあります。
1)楽しみを見つける
2)寄り添う人を見つける
3)記録を付ける
この他にも補助的に
4)小さな成功を積み上げる
5)環境を整える
6)意味づけを再確認する
ということが有効です。これらは、一種の仕組みです。「継続できない」とき、「意志の弱さ」として、自分を責めるのではなく、「継続する仕組み」を作りあげることが重要です。