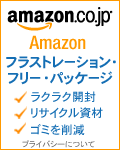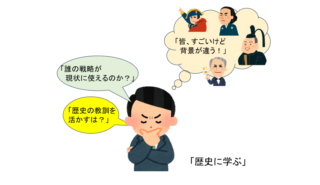転職決断をする前に考えて、「職種がイヤ」なのか、「仕事(タスク)がイヤ」なのか

転職決断をする前に考えて、「職種がイヤ」なのか、「仕事(タスク)がイヤ」なのか
あなたの「仕事がイヤ」は、「職種が嫌」なのか、「タスクが嫌」なのか?
「会社がイヤになってやめます」
「仕事がイヤなので転職をしたい」
こんな言葉をはいて、転職をする人がいます。今の時代、年齢やポジションに関係なく、転職を考える人が増えています。また、人手不足も背景ににあって、転職をサポートする会社が隆盛を極めています。
転職しようという理由が、
「もっと給料を上げたい」
「もっと、高いキャリアを積みたい」
といったポジティブなら、うまくいく確率が高いでしょう。ところが、冒頭に挙げたような、ネガティブな理由での転職は、受け入れる企業側として、歓迎しにくいものです。たとえ、転職できたとしても、しばらくすると再び「会社や仕事がイヤになる」ことが懸念されます。これは、転職癖のある人が持っている一つのパターンです。(個人的感想ですが。)
そもそも「会社がイヤ」とか、「仕事がイヤ」というのは曖昧な感覚です。「会社が嫌」と思っていても、それは「会社が嫌なのか」、「職種が嫌なのか」、自覚していないこともあります。よく考えると、会社は好きでも、職種(配属先)が嫌なこともあれば、会社そのものが嫌なこともあります。
また、「仕事が嫌」といっても、やっている「職種が嫌」と言う場合と自分の役割である「仕事(タスク)が嫌」と言う場合があります。
転職を検討する際に「職種が嫌なのか」「タスクが嫌なのか」を見極めることは、後悔のない意思決定をするためには重要です。職種とタスクに対する好き嫌いを分析し、自分の「嫌だ」という感情の構造を可視化し、感情的な衝動ではなく、戦略的な判断をすることが大切です。
転職を決断する前に、「仕事が嫌だ」という感情を以下のステップで分析してみてください。
1)自分の「嫌だ」を分解すること
2)「職種の嫌」と「タスクの嫌」から成るマトリックスを作る
3)マトリックスによる自己理解
「嫌だから辞めたい」という感情を、これらのステップを通して構造的に整理することで、転職理由を「逃げ」ではなく「戦略的な選択」に変えることができます。
広告

マイナビ転職2027オフィシャルBOOK 採用獲得のメソッド はじめての転職ガイド 必ず成功する転職
自分の「嫌だ」を分解する
現在の仕事に対して感じている「嫌だ」という感情は、2つに分けて整理することができます。
1)職種が嫌なのか?(業界・職務内容・役割そのもの)
2)タスクが嫌なのか?(日々の作業内容・人間関係・負荷)
このとき、「タスクの嫌」は更に3つのパターンがあります。それぞれについて、以下に述べます。
① 意味不明:タスクの目的や成果が不明瞭で、やりがいを感じない
「意味が分からない仕事」とは、業務の目的や成果が不明瞭で、自分の仕事が組織や社会にどう貢献しているのかが見えない仕事を指します。日本の企業では、年功序列や慣習に基づく業務が多く残っており、特に若手社員や新入社員にとっては「なぜこの作業をするのか」が説明されないまま業務を任されることが少なくありません。
また、上司からの指示が「とりあえずやっておいて」「前例に倣って」といった曖昧なものである場合、仕事の意味を見出すことが困難になります。仕事に対する納得感が得られず、モチベーションが低下し、精神的な疲労感が蓄積されます。
② 人間関係のストレス:上司・同僚との摩擦、空気の重さ、孤立感
日本の職場では、上下関係や同調圧力が強く、人間関係が仕事の満足度に大きく影響します。特に事務系一般職では、部署内の連携や調整業務が多く、上司・同僚・他部署との関係性が複雑になります。言いたいことが言えない、意見が通らない、理不尽な指示に従わざるを得ないといった状況が続くと、心理的なストレスが蓄積されます。
また、日本特有の「空気を読む文化」や「和を乱さないことを重視する風土」は、個人の感情や意見を抑圧する傾向があり、結果として職場の人間関係が重荷になることがあります。
③ 能力を超える負荷:スキル不足、量的過多、責任の重さ
「能力を超える仕事」とは、経験やスキルが不足しているにもかかわらず、高度な業務や責任を負わされる状況。或いは、量的にキャパをオーバーしている状態。日本企業では、配属や昇進が年次や人員配置の都合で決まることが多く、個人の適性や準備状況が十分に考慮されない場合があります。
また、教育や研修が不十分なまま業務を任されると、失敗への恐怖や自己否定感が強まり、仕事に対する苦手意識が形成されます。特に若手社員にとっては、周囲に相談できる環境がないと、孤立感や無力感が深まります。
「職種の嫌」と「タスクの嫌」から成るマトリックス
「職種が嫌」と「タスクが嫌」でマトリックスを作ると、以下のようになります。
|
|
タスクは嫌でない |
タスクが嫌 |
||
| 意味不明 | 人間関係 | 能力超過 | ||
| 嫌な職種ではない | ① 快適ゾーン ・職種もタスクも好ましい ・満足度が高い |
②-1 目的不明ゾーン |
②-2 人間関係摩擦ゾーン |
②-3 能力限界ゾーン |
| 嫌な職種 | ③ 職種不一致ゾーン ・作業は苦ではないが、職種に違和感 ・キャリアへの迷い |
④-1 二重虚無ゾーン |
④-2 二重摩擦ゾーン |
④-3 二重限界ゾーン |
このマトリックスに当てはめると、自分の「嫌さ」がどの象限に属するかが明確になります。各象限には、以下のような特徴と対処法が考えられます。
① 快適ゾーン(職種もタスクも好ましい)
高い満足度と安定したパフォーマンスが得られます。自発的な学習や改善意欲が湧き、周囲との協働も円滑
② 職種は嫌ではないがタスクが嫌
②-1(目的不明):職種は合っているので、タスクの意味を再定義するか、業務改善を試みることで解決可能。転職よりも社内異動や業務再設計が有効。
②-2(人間関係摩擦):職種は好きなので、職場環境の変更(部署異動、リモート勤務など)で改善できる可能性あり。転職は最終手段。
②-3(能力限界):職種への適性はあるため、スキルアップや業務量調整で乗り越えられる可能性あり。転職は慎重に。
③ 職種不一致ゾーン(作業は苦ではないが、職種に違和感)
「この仕事は自分らしくない」という違和感があり、キャリアの方向性に迷いが生じる。長期的な不満が蓄積しやすい。自分の価値観や志向性を棚卸しし、職種とのズレを言語化する。社内異動や職種変更の可能性を探る。
④ 職種もタスクも嫌
④-1(二重虚無):職種もタスクも意味を感じられない場合、根本的なキャリアの見直しが必要。転職は前向きな選択肢。
④-2(二重摩擦):職種も人間関係も苦痛なら、環境を変えることが最優先。転職によって心理的安全性を確保することが重要。
④-3(二重限界):職種も作業も能力的に限界なら、自己肯定感の回復とキャリア再設計が必要。転職と並行してリスキリングを検討。
マトリックスによる自己理解
このマトリックスは、単なる分類ではなく、自己理解と職場改善のための「問いの設計」にも活用できます。例えば、
「この仕事の何が嫌なのか? 職種か、タスクか?」
「嫌な部分は変えられるか? 変えられないか?」
「我慢する価値はあるか? 報酬や成長につながるか?」
といったことです。こうした問いを通じて、感情的な「嫌だ」から、構造的な「どうすればよいか」への転換が可能になります。
最終的に「転職すべき」と感じた場合でも、このマトリックスによって、「嫌だから辞めたい」という感情を、構造的に整理することができます。
広告
まとめ
「仕事がイヤ」と思う感情には、「職種が嫌」と「仕事(タスク)が嫌」という場合があります。「仕事が嫌だ」という感情を以下のステップで分析することができます。
1)自分の「嫌だ」を分解する
2)「職種の嫌」と「タスクの嫌」から成るマトリックスを作る
3)マトリックスによる自己理解
「嫌だから辞めたい」という感情を、これらのステップを通して構造的に整理することで、転職を「逃げ」ではなく「戦略的な選択」に変えることができます。