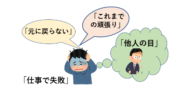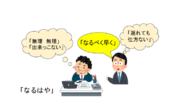幸福感を高めたいなら「接近的」で「内在的」な目標を立てよう

幸福感を高めたいなら「接近的」で「内在的」な目標を立てよう
2つの目標設定視点
アマチュアゴルファーは、池を前にすると、
「池に入れたくない」
とつい考えてしまいます。上級者やプロなら、
「あそこに打ちたい」
と目標地点に意識を集中します。結果は、そのプレイヤーの技量次第なのでしょうが、心理面では「あそこに打ちたい」と目標を設定した方がプレッシャーを少なくできます。
また、プレーする際
「優勝したい」とか「恥をかきたくない」
と考えれば、常にプレッシャーを感じ易く、
「自己ベストに近いスコア」や「プレーをエンジョイしたい」
と考えると気分的には楽になります。
プレー中に感じる精神的プレッシャーの差は、目標設定の仕方によって変わります。
目標を設定する際、2つの視点があります。
1)「接近的目標」と「回避的目標」
「接近的目標」とは、得たい結果に焦点を当てた目標。例えば、「◯◯したい」「成功したい」といったことです。
「回避的目標」は、避けたい結果に焦点を当てた目標。「◯◯になりたくない」「失敗したくない」といったものです。
冒頭の例で言えば、「あそこに打ちたい」は、接近的目標。「池に入れたくない」は、回避的目標です。
2)「内在的目標」と「外因的目標」
「内在的目標」は、個人の内的価値と結びついた目標。例えば、成長、健康、人間関係、自己実現などです。
「外因的目標」は、他者からの評価や報酬に基づく目標。経済的成功、外見、名声、承認などです。
ゴルフプレヤーでいえば、「プレーをエンジョイしたい」は、内在的目標。「優勝したい」は、外因的目標です。
幸福度という観点から考えると、「回避的目標」より、「接近的目標」の方が、高い傾向にあるようです。また、「内在的目標」の方が、「外因的目標」より、幸福度が上がる傾向があります。
目標設定の仕方によって、幸福度は大きく変わります。この記事では、目標設定の仕方が精神状態に与える変化を考えます。
なお、記事の内容は、「人を伸ばす力―内発と自律のすすめ」ロバート・デジ(新潮社)、「幸福優位の7つの法則」ショーン・エイカー(徳間書房)を参考にしています。

幸福優位7つの法則 仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論
目標設定における4象限モデル
目標を設定する際の2つの視点について、縦軸に「内在的目標」vs.「外因的目標」、横軸に「接近的目標」vs.「回避的目標」を取ると下図のようになります。

各象限の目標例と幸福度の関係を以下に説明します。
A象限:内在的 × 接近的目標
この象限は、最も幸福度が高くなります。自分の価値観と一致し、前向きな成長意欲に基づく目標が並びます。研究(Deci & Ryanの自己決定理論)によると、このような目標は「自律性」「有能感」「関係性」の3要素を満たし、持続的なモチベーションと高い主観的幸福感をもたらすと言われています。
健康目標を例にするなら、
「毎朝散歩をして心身を整えたい」「筋力をつけて快適に過ごしたい」
ビジネスなら、
「顧客の役に立ちたい」「新しいスキルを身につけたい」
ゴルフでは、
「自己ベストを更新したい」「楽しくプレーし、成長したい」
といった目標です。これらの目標は、自分の成長を実感しやすく、プレッシャーも少ないため、仕事やプレーそのものが楽しくなります。結果よりも、「成長感」が幸福に直結します。
B象限:内在的 × 回避的目標
この象限では、不安が内在し、幸福感はやや低下します。目標が内在的であるため、ある程度は本人の価値観に基づいていますが、焦点が「恐れ」や「不安」に置かれているため、ストレスや持続的な不安を伴いやすく、幸福感はやや低くなります。
たとえば、健康について、
「病気になりたくない」「太りたくない」
ビジネスでは、
「信頼を失いたくない」「顧客に迷惑をかけたくない」
ゴルファーなら、
「イップスになりたくない」「集中力を切らしたくない」
といったことです。
「癌になりたくない」という目標は、健康を守るという点では意味がありますが、意識が恐怖に引き寄せられているため、生活の質を下げる要因にもなり得ます。防衛的な行動は短期的には有効でも、長期的には「心の余裕」がなくなりやすいのです。
C象限:外在的 × 接近的目標
この象限の目標は、外的な評価や報酬を求めるため、一時的には高いモチベーションを得ることができます。しかし、他人との比較や成果への執着が強く、長期的な幸福感や満足感にはつながりにくいとされています。目標達成後の「空虚さ」や「もっと欲しい」という飽くなき欲望が、精神的安定を揺るがします。
例えば、健康目標として、
「見た目を良くしたい」「体脂肪を落としてモテたい」
ゴルフであれば、
「大会で優勝したい」「周囲にうまいと思われたい」
といったことです。また、ビジネスでは、
「昇進したい」「営業成績を上げて年収1000万にしたい」
という明確な目標となります。この種の目標は、短期的な行動力を高める効果があります。しかし、達成できなかったときの自己否定、達成しても満たされない「次の目標への焦燥」が生まれやすく、幸福感は意外と低くなることが多いものです。
D象限:外在的 × 回避的目標
この象限の目標は、他人の評価を避けるための「恐れ」によって形成されます。モチベーションの源が「罰回避」や「恥の否定」なので、心理的プレッシャーが非常に強く、幸福感は最も低いといえます。燃え尽き、うつ状態に繋がるリスクも高くなります。
例えば、健康について、
「太ってみっともないと思われたくない」
ビジネスでは、
「上司に怒られたくない」「営業ノルマ未達で査定が下がるのが怖い」
といった意識がプレッシャーとなります。また、ゴルフに当てはめれば、
「池に入れて恥をかきたくない」「他人に下手だと思われたくない」
という消極的な目標がつくられます。こんな気持ちでプレーすれば、自然なスイングができず、結果的に失敗を招きやすくなります。そして自己肯定感が低下し、ますますミスを恐れる悪循環に陥ります。これはビジネスにも通じます。
まとめ
目標設定には、2つの視点があります。
1)「接近的目標」と「回避的目標」と
2)「内在的目標」と「外因的目標」です。
その中で、内在的・接近的目標(A象限)は、最も幸福度を高める目標設定。一方、外在的・回避的目標(D象限)は、最もストレスが高く、幸福感が低下し易いものです。
今、自分の持っている目標が、どの象限にあるのか、一度考えてみてはどうでしょうか。
目標の再構築は、幸福への第一歩かもしれません。
参考記事:意味のある目標設定にするには、「結果目標」に「行動目標」を付けること
リーダーが、部下の目標を一緒に立てるときに注意すべき3つのポイント