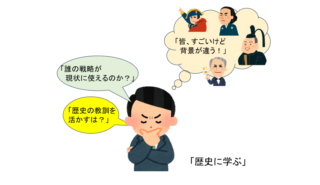問題の解決策が見つからない時は、「ラテラルシンキング」に切り替える
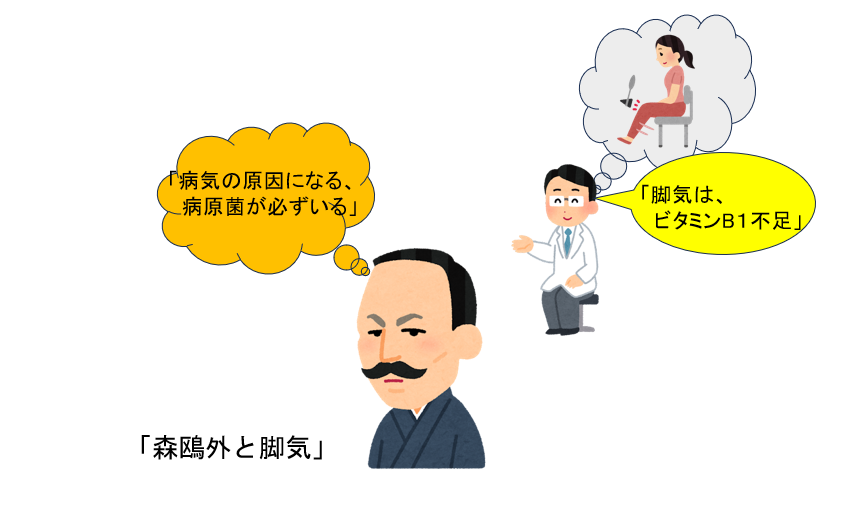
問題の解決策が見つからない時は、「ラテラルシンキング」に切り替える
「ロジカルシンキング」から「ラテラルシンキング」に舵をきった社長の例
「いくら安くしても、『100均』には勝てませんよ」
ある日、日用雑貨を製造している町工場の社長に向かって、取引先の問屋が発した言葉です。社長が、「ダイソー」に行ってみると、確かに自社製品と同様なものが、100円で売られていました。手に取ってみれば、出来栄えの違いはすぐわかります。しかし、機能としては、遜色ありません。社長は、
「良いモノは売れる」「値下げをすれば売れる」
ということで、これまで知恵を絞ってきました。
「『必要』が、知恵を生み出す」
という信念のもと、「知恵と努力」でこれまで危機を乗り超えてきたのですが、今圧倒的な価格差を前に、ようやく自分の発想そのものの限界に気付きました。
これは、町工場の社長が、自分の「発想の幅の狭さ」に気付いた例です。
人が問題にぶつかったときに行う思考プロセスがあります。例えば、以下のようなプロセスです。
1)問題の発生 「何か変だぞ」「大丈夫かな」
2)原因の特定 「なぜ、こうなるのだろう?」
3)過去の経験・知識と照らし合わせる 「前にも、こんなことあった」
4)初期的な解決策を思いつく 「とりあえず、こうしてみよう」
5)行動する 「試しにやってみよう」OR「もう少し、様子を見よう」
6)結果の確認 「うまくいった?」「ダメだった」
これは、「問題には必ず原因があり、それを見つけて取り除くか改善すれば解決する」という前提のもとに思考するプロセスです。人は、生まれたときから、家庭でのしつけや学校での教育などを通して、この思考プロセスに馴染んでいます。
この思考方法は、その人が意識しているかどうかは、わかりませんが、「ロジカルシンキング」といわれる思考方法です。問題をいくつかの要素に分け、真の原因に迫るといったアプローチです。これを、効率的に行う方法が、PDCAサイクルです。
ロジカルシンキングは、必ず原因があるような問題、例えば工場の設備異常や特定の商品売上減対策といった問題解決には、威力を発揮します。
ところが、もっと工場の設備異常頻度を下げたい、全社の売上を伸ばしたいといったとき、ロジカルシンキングでは、行き詰るということがあります。
冒頭に挙げた町工場の社長は、特定の商品を売るのではなく、会社として売上を伸ばす視点から「製造商品群を変える」「低価格では勝負しない」という考え方へ舵を切りました。
この社長は、「売上減少」という問題に対して、これまでのアプローチを変えて、「自社の従業員、設備、技術を活かすにはどうすれば良いか」という問題に置き換えて考えなおしました。「売上減少を食い止める」という問題を「何を作れば買ってもらえるか」と発想を広げたのです。その結果、自社の設備、技術で出来る売れそうな商品が次々にみつかり、今試作に励んでいます。
この社長の発想は、ラテラルシンキング(水平思考)と言われるものです。ラテラルシンキングとは、物事の角度を変えて多角的に考察し、新しい発想を生み出す思考法です。既存の概念や既成観念にとらわれず、自由な発想をするところに特徴があり、斬新な発想やアイデアが求められる際に効果を発揮すると言われています。
問題解決の壁にぶつかりラテラルシンキングに切り替えた方が良い場面でも、それができないことがあります。そこには、いくつか理由があります。
1)「正解信仰」から抜けられない
2)問題の「枠組み」自体を疑えない
3)「論理的に説明できないもの」、「偶然」を無視する
因果関係(ロジカルシンキング)からの解決に行き詰ったとき、上記のようなことを避けることで、ラテラルシンキングモードに移行して、問題解決を図ることが期待できます。
「正解信仰」から抜けられない
物事には、因果関係があり、問題解決には唯一の「正解」があるという「正解信仰」から抜けられないとラテラルシンキングのモードに移行できません。
「そもそも正解は、存在しないのかも知れない?」
「どこにも因果関係なんてないかも知れない?」
そんな、正解の存在や因果関係に対して「疑う力」がないとラテラルシンキングモードに入れません。
明治時代、陸軍軍医総監であった森林太郎(森鴎外)は、終生「脚気の原因は病原菌である」との考えから抜け出せませんでした。森は、ドイツ流の正統的医学を学び、そのプライドがあったためか「病気には、必ず原因となる病原菌が存在する」という立場を変えることはありませんでした。(参考記事:ダイヤモンドオンライン「日清、日露戦争で3万人以上が「脚気」で死亡…文豪・森鴎外の「大失敗」とは?」)
また、「失敗(不正解)=悪」という先入観が、規格外のアイデアや冒険を「リスク」としか捉えられず、飛躍した考え方ができないということがおきます。例えば、会議などで斬新なアイデアがでると
「現実的じゃない」
とすぐに却下してしまうような態度です。その結果、無難な案だけが残って何も変わらないということが起きます。
また、過去の成功体験から問題解決策を探すのは有効な方法ですが、「過去の成功体験」にしがみつくことはいけません。今起きている問題と過去に起きたこととの間には、似ていても違いがあります。ところが、違いを疑わず、前と同じ発想・行動をしてもうまく行きません。
問題の「枠組み」自体を疑えない
問題解決にばかり集中して、問題そのものを疑ったり、前提を変えたりができないとラテラルシンキングモードに移行できません。
冒頭に例を挙げた社長は、
「売れなくなった商品をどう売るか」
を問題として、値下げやコストダウンに努力を払っていたのですが、ダイソーで異次元の低価格を突き付けられて、問題を「会社としての売上増」に切り替えました。そして、視点をコストダウン一点張りから、「設備・技術・社員の有効活用」という視点に切り替えたのです。
問題の「枠組み」を変えるには、問題の本質を見抜く力が必要です。一種の抽象化です。問題と考えていることの本当の問題、本当に実現したいことは何かを再定義できることが、ラテラルシンキングに移行する上で大切です。
「論理的に説明できないもの」、「偶然」を軽視する
アイデアや可能性に「理屈」を求め過ぎたり、直感や偶然を軽視したりする態度は、発想を狭くします。
オリジナリティや論理性を求められる基礎研究の分野で、発明発見の経緯を詳細に調べてみると「模倣」と「偶然」が大きな割合を占めていることが分かります。研究開発のブレイクスルーに関し、高松秀樹著「研究開発物語 創造は天才だけのものか―模倣は創造への第一歩」(化学同人1992年)があり、化学・医薬品に関する大きな発見・発明についてその過程を調査しています。そして、その40%は「模倣」であり、同じく40%は「偶然」であったと結論付けています。「模倣」は「理論的」とされ、「偶然」は「オリジナリティ」とか「セレンディピティ」と言い替えることができます。
理論的に考えようとするあまり、事実が見えないということが起きます。長い時間を考えると、偶然はどの人にも同じように起きるはずですが、これを利用できるかどうかは、その人の発想にかかっています。
森林太郎は、「理屈は分からないが、海軍は麦飯を食べていて脚気になる兵がいない」という事実を聞いていたのですが、これを「偶然」として軽視して、何万もの陸軍兵を死なせる結果となってしまいました。
広告

創造は天才だけのものか: 模倣は創造への第一歩 研究開発物語
まとめ
問題解決の壁にぶつかりラテラルシンキングに切り替えた方が良い場面でも、それができないことがあります。そこには、いくつか理由があります。
1)「正解信仰」から抜けられない
2)問題の「枠組み」自体を疑えない
3)「論理的に説明できないもの」、「偶然」を無視する
因果関係(ロジカルシンキング)に行き詰ったとき、上記のようなことを避けることで、ラテラルシンキングモードに移行して、問題解決を図ることが期待できます。