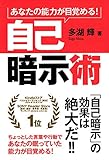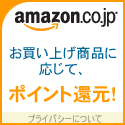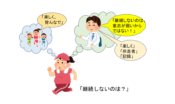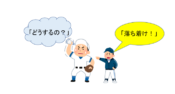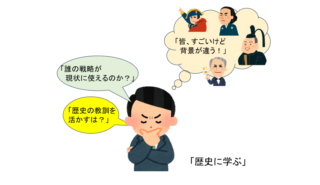野球の投手は「始動型」、打者は「受動型」、その特徴とイップス
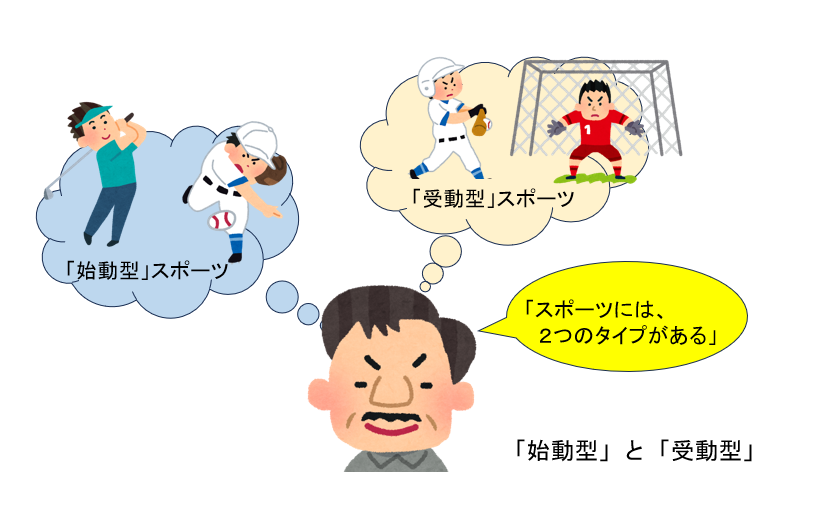
野球の投手は「始動型」、打者は「受動型」、その特徴とイップス
スポーツには、「始動型」と「受動型」がある
「野球のピッチャーと打者の違い」
「ゴルファーとゴールキーパーの違い」
「打者とゴールキーパーの共通点」
この答えは、ピッチャーやゴルファーは「始動型」であるのに対して、打者やゴールキーパーは「受動型」ということです。
スポーツには大きく分けて2つのタイプがあります。ひとつは「始動型」、もうひとつは「受動型」です。これは競技者が自ら動作を開始するか、外的状況に反応して動作を開始するかという違いに基づく分類です。始動型か受動型かによって、心理的準備、戦略、集中の質に大きな違いが生まれます。
始動型のスポーツには、野球のピッチャー、ゴルフ、陸上競技のやり投げや走り高跳びなどのフィールド競技があります。一方、受動型スポーツには、野球の打者、サッカーのゴールキーパー、陸上競技の短距離走などのトラック競技があります。
始動型と受動型の違いから、競技者には心理面で異なったものが求められます。
また、イップス(Yips)といわれる、出来るはずの動作が突如としてうまくできなくなる現象は、ゴルフのパッティングや野球の投手など始動型スポーツで起こります。
仕事においても、研究者や企業家は「始動型」、営業職や医療現場は「受動型」と分類することができます。それぞれに必要なスキルに加えて、始動型、受動型特有の精神的側面が求められます。
この記事では、始動型と受動型の違いと求められる精神的側面について考えます。
「始動型」スポーツの特徴とイップス
始動型スポーツとは、競技者が自らの意思で動作を開始する競技。代表的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
1)野球のピッチャー:投球のタイミングを自分で決める。
2)ゴルフ:ショットの開始は完全に自分の裁量。
3)陸上のフィールド競技:助走や投てきのタイミングを自分で調整する。
始動型スポーツでは、動作前に「準備の時間」が存在します。選手は自分のリズムで集中を高め、イメージ作りや自己暗示を行っています。たとえば、プロゴルファーが「このショットはフェアウェイに乗る」といった自己暗示することで、筋肉の緊張を緩め、動作の精度を高めることができると言います。
しかし一方で、準備時間が長い分、思考が過剰になりやすく、「失敗してはいけない」というプレッシャーが高まることがあります。自己暗示が強迫的であったりすると、動作が硬直するリスクが高まります。
受動型スポーツに多いイップス
イップス(Yips)とは、本来できる動作が突如としてうまくできなくなる現象で、筋肉の硬直や過剰な意識によって動作がぎこちなくなる状態を指します。特にゴルフや野球の投手など、始動型スポーツにおいて多く報告されています。
始動型スポーツにイップスが多いのにはいくつか理由があります。
1) 自己主導性による「責任の重さ」
始動型スポーツでは、動作の開始を自分で決定するため、成功・失敗の責任がすべて自分に帰属するように感じます。例えば、ゴルファーがパットを打つ瞬間や野球のピッチャーが投球する瞬間、弓道では矢を放つ瞬間です。
これらの場面では、周囲の状況が静まり返り、注目が一点に集中するため、心理的プレッシャーが極度に高まります。この「自分から始める」という構造が、過剰な自己意識を生み、動作の自動化を妨げると考えられます。
2) ルーティン依存と微細なズレへの過敏性
始動型スポーツでは、選手が自分のルーティンを持ち、それに従って動作を行っているということが多いようです。例えば、ゴルファーが打つ前に毎回同じ回数素振りをする、ピッチャーが投球前に同じリズムでロジンバッグを使うといったことです。このようなルーティンは集中力を高める一方で、わずかなズレが「違和感」として認識されやすくなります。違和感が意識に上ると、動作が「意識化」され、無意識的な運動制御が妨げられます。これがイップスの発症メカニズムの一因と言われています。
3)動作の「静的開始」による思考の過剰化
始動型スポーツでは、動作前に「静止状態」が存在します。このため、以下のような心理になります。
1)動作前に考える時間があるために不安や失敗のイメージが入り込む
2)「失敗してはいけない」という自己暗示が強まり筋肉が硬直する
3)「正しくやらなければ」という完璧主義から動作がぎこちなくなる
これらのことから、静的な開始は思考の過剰化を招き、動作の流れを断ち切る要因となります。
「受動型」スポーツの特徴と心理
受動型スポーツとは、相手や環境の動きに応じて反応する競技です。代表的な例として、以下のようなものがあります。
1)野球のバッター:ピッチャーの投球に反応してスイングする。
2)陸上のトラック競技(短距離走など):スタートの合図に反応して走り出す。
3)サッカーのゴールキーパー:シュートされたボールに反応してゴールを阻止する
受動型スポーツでは、瞬間的な判断力と反応速度が求められます。自己暗示として、「冷静に対応できる」「相手の動きを見極められる」といった形で使われることもが多くあります。例えば、ゴールキーパーが「自分は相手のフェイントに惑わされない」と自己暗示することで、反応の精度が高まるといったことです。
受動型では予測不能な状況が多く、自己暗示が固定的すぎると対応力を損なう可能性があります。「外角低めを狙う」と決め打ちしていたバッターが、内角高めに対応できないといったケースです。いくら準備をしていても、柔軟性と即応性がより求められます。
「4番サード長嶋茂雄」と「二刀流大谷翔平」
読売巨人軍の故長嶋茂雄は、典型的な受動型に対応したプレーヤーでした。彼の身上は、来た球を無心で打つ、守備では3塁付近に来た球に無心で飛びつくことです。(少なくともそう見えました。)彼は、打者としても3塁手としても、野生的と言われる反応を示し、見事に受動型のプレーをこなしていました。
大リーグで活躍する大谷翔平は、投手と打者との二刀流です。投手としては、始動型、打者としては受動型のプレーが求められます。異なる要素を求められることをどちらでも一流ということは、大変なことだと改めて分かります。彼の打席を見ていると対戦投手ごとに微妙に異なる打ち方をしていると解説する人がいます。ボールが来てから振り抜く長嶋流の受動型プレーヤーに対して、考えてから構える大谷流バッティングには始動型的要素が混ざっていると言えるかも知れません。
始動型・受動型を仕事にあてはめる
始動型、受動型というスポーツの分類は、仕事のスタイルにも応用できます。仕事に適応してみると以下のように分類できます。
1)始動型の仕事:自ら企画・推進する業務
例として、新しい事業や企画を立ち上げ、ゼロから構築する起業家やプロジェクトマネージャー。自ら自ら課題を設定し、仮説検証を進める研究者や開発者。
これらの仕事では、自分のペースで思考を深め、計画を立てる力が求められます。「自分のアイデアには価値がある」「自分が流れを作る」といった自己暗示が使われ、創造性と主体性を支えます。
2)受動型の仕事:外的要因に対応する業務
例としては、顧客の問い合わせに即時対応するカスタマーサポート、患者の状態に応じて迅速に対応する医療従事者や救急隊員、顧客の求めに対応する営業職などがあります。
これらの仕事では、状況判断と柔軟な対応力が求められます。「どんな状況でも冷静に対応できる」「相手の立場に立って考える」といった形の自己暗示が使われ、瞬発力と共感力を支えます。
まとめ:タイプに応じた自己理解
「始動型」と「受動型」という分類は、スポーツだけでなく仕事にもあります。始動型では「自ら流れを作る力」、受動型では「状況に応じて対応する力」がより求められます。自分がどちらのタイプに近いかを理解することで、より効果的な自己管理とパフォーマンス向上が期待できます。