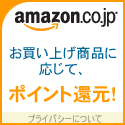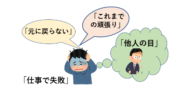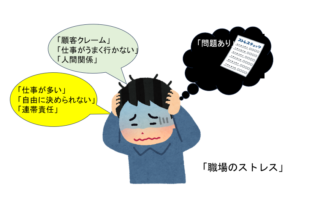「結論しか言わない」「結論しか聞かない」人々が生まれる3つの要因

「結論しか言わない」「結論しか聞かない」人々が生まれる3つの要因
「結論しか言わない」「結論しか聞かない」人々が生まれる3つの要因
「報告や会話は、結論から話すこと」
これは、報告や会話において、心得ておくべきこととして教えられます。ところが、最近は、結論の後、その理由、データなど根拠を示すべきところを「結論しか言わない」人が多くいます。また、受け手も「結論しか聞かない」という人が増殖しているように思えます。
例えば、TVのワイドショーやSNSのコメンテーターは、「結論しか言わない」ことが多々あります。例えば、大雨や猛暑に対して原因を聞かれ、
「これは、地球温暖化のため」
と簡単にコメントします。
また、コメンテーターのコメントをTVやSNSを通して聞く方も、たとえ理由の説明があったとしても「結論しか聞かない」という人だらけです。例えば、政治や企業における不祥事が報道されると、そこに至った経緯や事情の説明は無視され、
「○○専務の独断で決めたことが問題である」
といった具合に結論のみが受け入れられるといった具合です。その挙句に「○○専務は、極悪人」といったことがSNSに溢れてしまいます。他にも、誰かの発言を切り取ってネットなどで流れると、前後の状況に関係なく「差別発言をした人」などと「炎上」、発言者が謝罪や職を辞することさえ起きています。
これら、「結論しか言わない」「結論しか聞かない」ということでは、問題解決にならなばかりか、むしろSNS上での「炎上」や「バッシング」など問題拡大になりかねません。
そもそも「結論から話す」ことが推奨されるのは、以下のような理由があります。
1)結論を強調できる
結論から話すメリットは、伝えたい結論が会話の中に埋もれてしまうことを防ぐことができる。
2)聞く人が結論を踏まえて話を聞ける
聞き手は、知りたいことを最初に聞くことで、心構えを持ってその後の話を聞くことができ、より理解度が高まる。
3)結論の伝え漏れを防止できる
最後に結論を話そうとしていても、途中の話に埋もれたり、単純に時間切れが起きたりして結論が話せなくなることが防げる。
これらの理由で、「結論から話す」ことが推奨されていますが、「結論だけでいい」ものではありません。結論に至る過程や理由、証拠・データなどが、その後に話されなくていけないのですが、最近は伝える方も受け取る方も「結論だけ」といったことが多くなっているのが実情です。
「結論しか言わない」「結論しか聞かない」といったことが起きるのは、以下の3つの要因が関係しています。
1)社会的風潮
2)「バイアス」
3)教育
これらが背景となって、
① 根拠が検証されないまま結論だけが広がる
② 異なる立場同士での理解の共有が困難
③ 誤情報や偏見が強まる
といった問題が発生しています。
この記事では、「結論しか言わない」「結論しか聞かない」原因を探り、その問題点を考えます。
広告

99%はバイアス
「時間短縮」という社会的風潮
現代社会は、情報に溢れています。既存のメディアであるTVや新聞に加え、SNSや動画サイトが物凄い量の情報を流しています。そんな情報の中にいる人々は、時間の制約、面倒くささなどから、「理由はいいから結論を知りたい」という態度に成り勝ちです。世の中、時間短縮、コスパの良さを重要視することが社会で広がっています。
世の中に溢れる情報の中、SNSやYouTubeなどの発信者は、「視聴者に見てもらえる」ことを優先します。その結果、「1分でわかる○○の真実」といった伝え方をします。つまり、「より短く内容を伝える」、「より興味を引くタイトル」といったことが重視されます。その結果、記事であれば最初の数行、動画であれば最初の数秒で結論を伝えようとします。こうした形式は、詳細な理由や背景説明をそぎ落としてしまいます。一方、受け手もそれに慣れてしまい、「詳細は後で調べよう」ということは、まずありません。
TVなどのメディアに登場するコメンテーターは、限られた時間内で視聴者の関心を引き、印象的なメッセージを残すことが求められます。そのため、複雑な背景や多面的な議論よりも、明快な「結論」を提示する傾向が強くなります。
例えば、
「地球温暖化のため、○○はやめるべきだ」
「企業不祥事の原因は、専務が独断で○○を決めたことにある」
と言った発言は、視聴者に強い印象を与えると同時に思考の余地を奪っています。背景にある科学的根拠や制度の問題、代替案の検討などは省略され、結論だけが切り取られてしまいます。
一方、聴衆は情報の受け手として、結論だけを聞き取り、それをもとに自らの意見を展開します。これは、情報過多の時代において、効率的に判断を下すための知恵でもあります。例えば、
「地球温暖化が深刻なのに、火力発電は無責任だ」
「独断で決める上司はパワハラだ」
などと、聴衆はコメンテーターの結論を自分の価値観に照らして再構成し、あたかも自分の意見であるかのように拡散させていきます。
集団同調と自己正当化
同じ結論を共有する集団の中では、理由が曖昧でも「多数派がそう言うなら正しい」と感じやすくなります。さらに、自分の信念と矛盾する事実を避け、現状維持を選びやすくなります。
SNS文化の中、フォロワー数の多い人物は、その権威性から「結論は正しい」と受け止められやすくなっています。理由の提示がなくても、「この人が言うなら正しいはず」という心理が働き、検証が省略されます。
また、SNSやネットニュースのレコメンド機能は、ユーザーが好む意見や傾向を強化します。結果として、自分の意見に合致する結論ばかりが提示され、「理由は自分で勝手に補完する」状態を加速しています。
発信者、受け手の双方にある「バイアス」
「結論だけ発信する人」、「結論を聞くだけ納得する受信者」になる背景には、双方にバイアスがあるからです。
心理学でいうバイアス(bias)は、「事実や論理とは別に、認識や判断に偏りを生じさせる心の傾向」です。人間の認知は、限られた情報処理能力を補うために、ヒューリスティック(直感的判断)を用います。これが、できるのは、バイアスがあるからです。代表的バイアスとして、以下のようなものがあります。
1)確証バイアス:自分の信念に合致する情報だけを選び、反する情報を無視する。
2)代表性ヒューリスティック:ある事例を全体の代表とみなし、過度に一般化する。
3)感情バイアス:怒りや不安などの感情が判断を歪める。
例えば、「地球温暖化防止のため」という言葉は、環境保護という正義感に訴えるため、感情バイアスを刺激します。また、「独断=悪」という構図は、民主主義の理想像に基づく代表性ヒューリスティックによって強化されています。
発信者と受け手は、双方が気づかないうちに自分のバイアスを強化するループに入りがちです。そのループとは、以下のようなものです。
1)発信者は、受け入れられやすい結論を選び、理由を省く
2)受け手は、自分のバイアスに沿った理由を勝手に補う
3)受け手がSNSや会話で拡散し、さらに簡略化された結論が広がる
4)発信者は「自分の主張は支持されている」と確信し、同様の発信を繰り返す
5)双方のバイアスが強化され、事実検証の余地が縮小する
この結果、誤情報の固定化、偏った解釈の固定化を招いていきます。
「結論」を求める学校教育
社会的風潮、バイアスが生まれる背景には、学校教育があります。
日本の学校教育は長らく「正解を導くこと」に重きを置いてきました。入試制度に代表されるように、限られた時間内に正しい答えを導く能力が評価される構造です。これは、論理的思考力や探究心よりも、効率的な情報処理と結論の提示を優先します。
試験問題も、自由記述や討論より選択式や穴埋め式の問題が多く、複雑な思考を促す機会が少なくなっています。この結果、生徒は「なぜその答えになるのか」よりも「どうすれば早く正解にたどり着けるか」に意識を向けるようになります。
このような教育環境では、「結論だけを求める」姿勢が無意識のうちに醸成され、社会に出た後もその思考様式が継続されているのではと思えます。
欧米の教育では、ディベートやディスカッションなどを通じて「結論の裏にある理由」を筋道立てて説明する訓練が重視されます。特に大学生では、論理的議論ができることが求められます。
しかし、日本では、意見形成や議論の訓練が限られており、自分の結論を支える根拠を集める、反対意見への対応を考える、誤った前提を修正するといったスキルが、十分育っていないのではないでしょうか。
もっともSNSなどを見ていると、欧米人といえども論理性のない意見を展開する人もいて、教育だけで「結果」重視の原因を押し付けられないとことが分かりますが。
学校生活では「みんなで同じ方向に進む」ことが重視されます。理由を問うことは、時に「空気を読まない行為」とされがちです。結果として、「結論への同調」だけが求められ、理由や根拠を共有する文化が育ちにくくなっています。
まとめ
「結論しか言わない」「結論しか聞かない」といったことが、マスメディアやネット上で起きています。その原因は、以下の3つ要因が関係しています。
1)社会的風潮
2)「バイアス」
3)教育
これらが、背景となって、
① 根拠が検証されないまま結論だけが広がる
② 異なる立場同士での理解の共有が困難
③ 誤情報や偏見が強まる
といった問題が発生しています。
参考記事:「投影バイアス」が強い人と会話すると不愉快に感じる理由
ショートカット思考の「ヒューリスティック」をマーケティングに活用するには