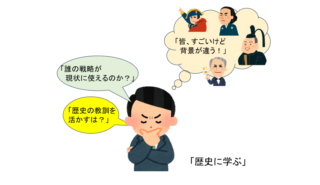人々の持つ漠然とした「不安」に対する3つの過剰反応の例
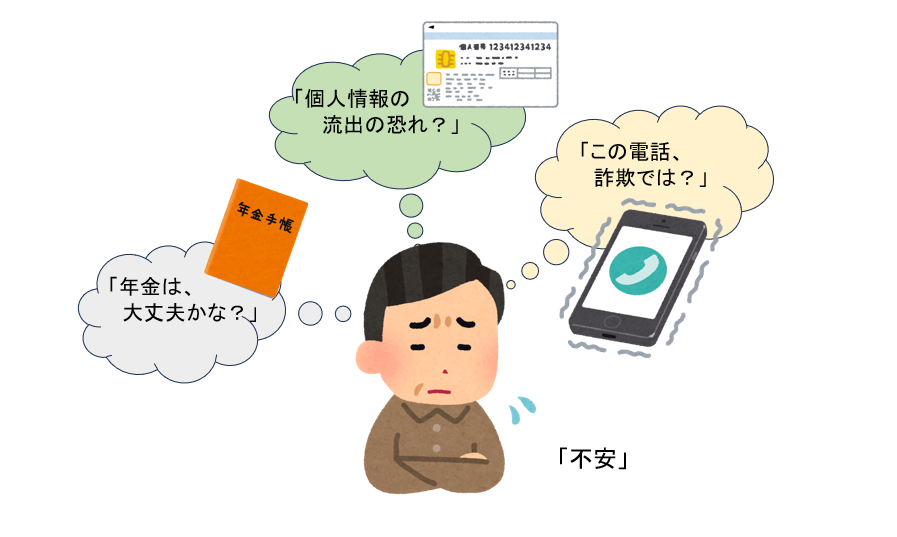
人々の持つ漠然とした「不安」に対する3つの過剰反応の例
人は、「不安」によって「行動する力」が出ると同時に過剰反応もする
「詐欺に遭うかもしれない」
「個人情報が漏れるかもしれない」
「将来、十分な年金をもらえないかもしれない」
これらは、日本人が抱える代表的な「不安」ではないでしょうか。こうした漠然とした不安は、個人の心理だけでなく、社会全体の行動様式や制度、メディア報道にまで影響を及ぼしています。
例えば、マスコミに詐欺事件のニュースがたびたび取り上げられることで、視聴者が詐欺に注意するようになる一方で、過剰に反応して、必要な連絡(行政や学校からの連絡など)が取れないといったことが起きています。
「進化心理学」という学問では、人間の脳は生存と繁殖を目的に進化してきており、その過程で、「不安」や「恐怖」に反応する傾向が備わっているとされています。これは古代において、生死を分けるようなリスク(猛獣や毒物、部族間抗争など)に即座に対応するために有効でした。進化心理学では、
「人は、『不安』によって動く」
とまで言っています。(堀田秀吾著「最先端研究で導きだされた『考え過ぎない』人の間が方」サンクチュアリ出版より)確かに人は、「失敗の不安があるから頑張る」、「彼女(彼氏)に嫌われる不安があるから見栄を張り努力する」といったことを思い浮かべると納得できます。また、「騙される」、「他人に利用される」といった不安があるから、注意を怠りません。国家規模でいえば、他国に侵略される不安から巨大な軍隊組織を持っています。
「不安」や「恐怖」に対する敏感な反応は、古代において、生死を分けるようなリスク(猛獣や毒物、部族間抗争など)に即座に対応するために有効でした。ところが、現代においては、リスクに対する過敏な反応が、時に非合理な行動や、過剰防衛、社会的不信を生む要因にもなっています。
例えば、日本には、
1)詐欺に対する不安
2)個人情報流出不安
3)将来の年金に対する不安
といった漠然とした「不安」が、世代によって強弱はありますが、広がっています。これらの不安に対して、適切に対応することが求められます。しかし、過剰反応してしまうことで、社会的な不信やトラブルが起きています。この記事では、これら「不安」からくる現象とその対処法を考えます。
広告

最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方
詐欺に対する不安
毎年、オレオレ詐欺や還付金詐欺などの「特殊詐欺」が多発しています。2024年の警察庁データ:「警視庁 特殊詐欺ページ」によると、特殊詐欺は全国で2万1千件、被害総額は718億円に上り、特に70代、80代の高齢者が被害者の中心を占めています。詐欺の常套手段は、「あなたの孫が事故を起こした」「税務署から返金があります」など、受け手の不安を切迫感のある言葉で煽り、判断力を奪う手口です。
一方で、詐欺を恐れるあまり、「知らない人はすべて詐欺」と考える過剰防衛の傾向が見られます。例えば、訪問営業や行政の戸別調査などにも過敏になり一切拒絶するような事です。高齢者が、「騙されるのでは?」という不安から、極度に人との接触を避けて「孤立化」、孤独死のリスクが生じるといったこともあります。
詐欺に対する過剰な不安に対して、
① 行政や企業による「詐欺ではない接触」の様式統一(身分証提示、公式番号での事前連絡)
② 家族間での「騙されない約束」の再確認
③ 地域コミュニティでの情報共有
といったことが望まれます。
個人情報流出への不安
マイナンバーカードの普及率が政策目標に届かない一因に、「情報が漏れるのではないか」「国に管理されるのではないか」という不安があると言われています。例えば、2023年のマイナ保険証の誤登録問題では、制度への信頼がさらに揺らぎ、多くの人が利用停止を申請する騒ぎとなりました。
また、スマホ決済やポイントアプリにおいても、名前や住所、クレジット情報がどのように扱われているか不透明であるとの印象から、高齢者の利用が進まないと言われています。これらのことから、日本ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の進行が遅れ、行政や医療の効率化に支障が出ています。信頼に基づく情報共有ができないと、社会全体のスピードが鈍化することになります。
対策として、個人情報利用の「見える化」とトレーサビリティの提供(いつ・誰が・なぜ使ったかを確認可能にする)や政府や企業による透明性の高い説明責任が求められます。
将来の年金に対する不安
内閣府のデータによると、日本の60代以上の高齢者は金融資産を多く保有しているにもかかわらず、将来不安から「使わない」「贈与もしない」傾向が強く、経済の循環を停滞させていると言われています。
また、現役世代では、「将来、十分な年金はもらえない」という不安があります。生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査 2024年」によると、日本の生命保険加入率は約80%です。他国と比較して、「保険の好きな国民」と言えます。また、「個人型確定拠出年金」「外貨建て年金」「個人年金」など、多数の将来備え商品が販売されており、加入者側も「老後が不安だからできるだけ備える」という姿勢です。
この「ため込み」は日本経済の消費停滞の一因であり、同時に親世代から子や孫世代への経済移転(相続や贈与)を妨げる要因にもなっていると言われています。
年金財政に関する「悲観的な情報の過剰発信」の是正や将来設計に基づいた「ライフプランニング支援」の充実などが望まれます。
まとめ
日本人が抱える詐欺、情報、老後に対する不安の多くは、人類共通の進化的心理傾向に根ざしています。それ自体は悪いことではなく、「用心深さ」「慎重さ」という形で、生存に寄与してきたと考えられます。しかし、現代の日本社会では、この防衛本能が過剰に作動し、社会的信頼、経済活動、制度運用を阻害する「副作用」を生んでいます。
不安をゼロにすることはできませんが、「仕組みで制御する」「情報で安心させる」ことは可能です。進化心理学的な視点から、「なぜ不安になるのか」ということを理解し、その上で対処することが、肝要と考えます。
参考記事:「漫然とした不安」を「安心」に変える3つのポイントとは